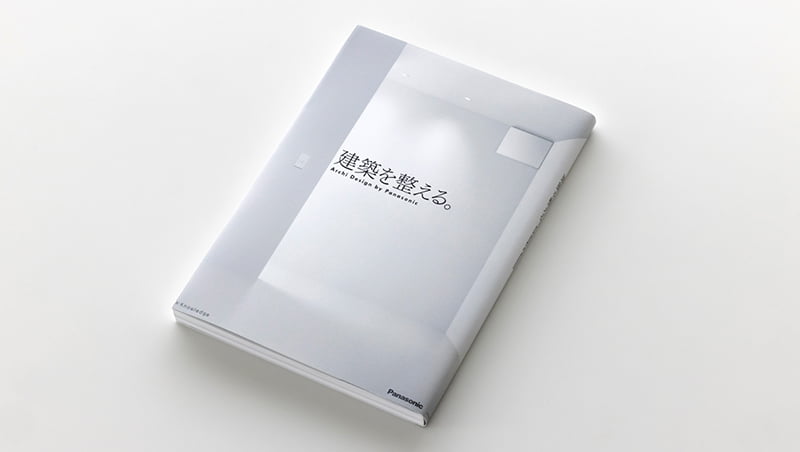電気設備を建築的視点で考えるパナソニックの思想「 Archi Design」をテーマにした書籍が発売されました。活躍する建築家8組へのインタビューや、実際の設計事例などを掲載。内容を一部ご紹介します。
建築を整える。
「住む」「働く」「商う」「泊る」。
こうした日々の営みを支える
建築のデザインは、どうあるべきか。
それぞれの建築において
確かな腕をもつ設計者に、
その整え方を問いかけます。
住む

暮らしに
寄り添う家のつくり
家族の暮らしの舞台である個人住宅において設備とはどんな存在か。建築家は暮らしと設備をどのように架橋したデザインをするべきだろうか。リオタデザイン・関本竜太氏が語る。

個と全体が
響き合う住まい
集合住宅とは、さまざまな住まい手やライフスタイルを受け入れる器である。数多くの集合住宅を手がける伊藤博之氏は、個性豊かな住空間をどのようにまとめ上げているのだろうか。
働く

自然とのつながる環境で
働く意味
オフィスの環境は閉じて設備で制御するほうが簡単で効率的かもしれない。しかし、それは本当の意味で快適な環境を整えたといえるのだろうか。自然とのつながりを通して歓びを感じられる空間設計を目指す川島範久氏に訊いた。

日々の営みが潤う
オフィスの表情
適切な距離感や落ち着きを備え、働く人たちが自然に居心地のよさを感じられるオフィス空間を目指しているとFLOOAT・吉田裕美佳氏は話す。こうしたデザイン思想は、どのように培われたのだろうか。
商う

人が自然に集う
現象の建築
商業施設の設計では、お店の個性を際立たせつつ地域の風景とも調和するように、繊細なバランス感覚が必要だ。厳しい条件のなかで永山祐子氏は、どんなことに気を配りながら個性的な建築を生み出しているのか。

成瀬・猪熊建築設計事務所
“シェア”を可視化する
豊かな色彩
成瀬友梨氏、猪熊純氏は店舗設計においては、建築家としての作家性にはとらわれず、各ブランドイメージに最適な提案をすることが自分たちの役目だと話す。個性的な店舗空間において設備を調和させるヒントを訊いた。
泊る

人をおもてなす
手仕事と照明
小嶋伸也氏、小嶋綾香氏は日本と中国を拠点に数多くの宿泊施設の設計を手がけている。素材の手触りや質感に強くこだわる2人は、人工的な設備とどのように対峙しているのか。

佐々木達郎建築設計事務所
旅の記憶を彩る
額縁としての宿
日常から離れて出合う旅先の景色を美しく引き立たせる宿泊施設とは。心地よい非日常の時間のために設備に求められることとは。佐々木達郎氏にうかがった。
Archi Designで整える。
建築と設備の調和とは何か。
その調和を実現するには、設備はどうあるべきか?
「Archi Design」という1つの思想に基づいて、
建築と設備の幸福な関係を探ります。


建築の色彩に合わせて
設備の存在を消す
成瀬・猪熊建築設計事務所
特に店舗の空間デザインでは、象徴的な色使いを大切に。
こだわって選定した空間の色彩を損なわないようにデザインとして気になる箇所の設備器具にはすべて特注色を指定。
現場で丁寧に検討・調整しよう。


ダウンライト類は
散らすと違和感がない
川島範久建築設計事務所
経済性も重要なポイントになる賃貸オフィスの設計で、ダウンライトは使い勝手がよい頼れる存在。
適切な間隔でグリッド状に配置し、数の多さをうるさく感じさせず、ほかの設備器具との調和も図れる。


化粧ダクトで空間を分節する
リオタデザイン
一面をすっきりときれいに見せたい、高さと勾配を生かした天井。
スポットライトやペンダントライトは、梁のように化粧したライティングレールに設置。位置変更や交換がしやすく、空間にリズムも生まれている。


天井を彫り込んで
ダクトの凹凸を消す
伊藤博之建築設計事務所
器具の位置をフレキシブルに変更できるライティングレールは、さまざまなライフスタイルに対応する必要のある集合住宅では重宝する。
空間にノイズを生まないようにライティングレールを天井面に揃えてフラットに納めると美しい。


サインとインターホンの
大きさ・位置を揃える
佐々木達郎建築設計事務所
カメラやボタン、スピーカーなど要素が多く、建物の顔であるエントランスではノイズになりがちなインターホン。
サインに合わせたカバーを製作し、すっきりと溶け込ませたい。


EPSも整然とした設えに
小大建築設計事務所
存在感の強いEPS(Electric Pipe Space)は空間デザインと調和せず違和感が発生しがち。
天井いっぱいまでの壁面を使用し、スリムにレイアウトしたことで整然と見せている。


何もないシンプルな天井を
可能にする間接照明
永山祐子建築設計
照明をはじめ、一切の電気設備を設置せず、吹抜けの空間にかかる大天井をノイズのない状態に。
天井高を感じさせない広がりのある空間を実現している。


エアコンと天井の間に
間接照明を仕込む
日吉坂事務所
壁掛けエアコンに必要な空気を吸い込むための上部のクリアランスをうまく利用して、間接照明(コーブ照明)の光を柔らかく広げる。
設備の露出を避けて天井面や壁面をすっきりと保ちつつ、明るく奥行きのある空間に。


空調用のスリットを
ライン照明に生かす
FLOOAT
オフィスの天井では、空調設備と電気設備の取合いが非常に難しい。
エアコン本体は天井内に納めながら、間口にスリットと照明を設置し、設備の露出を最小限にすることで天井面を美しく保つ。
群として整う。
「Archi Design」という
電気設備を建築視点で考える思想に
もとづいて誕生した商品。
それらは群として、
これからの建築を意匠・環境の両面で
美しく整えます。