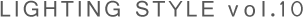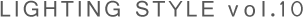

■物件概要
名称:京都大学医学部附属病院 南病棟
発注者:国立大学法人 京都大学
設計・監理:国立大学法人 京都大学
基本・実施設計:株式会社 内藤建築事所
施工:清水建設 株式会社
電気工事:株式会社きんでん
構造:鉄筋コンクリート造・一部鉄骨造(免震構造)
階数:地下1階・地上8階
延床面積:約2万2700m2
病床数:414床(個室126室、4床室72室)
開院時期:2015年12月
PDFをダウンロード



爽やかな朝の光から、徐々に色を深めてゆく夕日まで、太陽の光は刻々と変化していく。
人間も、自然光の流れに合わせて24時間の生体リズムに調整しているとされる。
京都大学医学部附属病院南病棟で採用された「ホスピタル・サーカディアンシステム」は、一日の生活リズムに合わせて病室の光環境を制御し、単調になりがちな入院生活にメリハリをつけ、サポートする。
蛍光灯を使う従来のホスピタル・サーカディアンシステムに、LEDによる波長制御技術を加えて、自然な光の変化を重視しつつ、患者の生活シーンや回診・看護シーンに合わせた光環境を構築した。

精神的・身体的なケアに加えて、より良い環境を整えることで患者の治癒力や回復に寄与できる――。
そうした病院の考えに基づき、快適な看護環境を提供する1つのアイテムとして導入された。


パナソニックのプロジェクトチームは、自然光の変化をベースに、南病棟に適した照度や色温度、スケジュールなどの設定を検討した。現場のモデル病床にシステムを持ち込み、患者の行動や、診療に必要な明るさなどをもとに検討した1日のスケジュールを提案。竣工後には、すべての病室で、照度や色温度の変化、視認性などを、病院関係者に確認してもらいつつ微調整も加えて、最終的なシステムを完成させている。季節によって日照時間が大きく異なるため、夏・冬・春秋の3つのパターンを切り替える。
照明ソフト技術
蛍光灯時代から20年近く培ってきた
サーカディアンライティング研究
20年近く前、まだ蛍光灯が中心だった時代から、パナソニックは医療・高齢者福祉施設のサーカディアン照明に着目して、研究と実績を重ねてきた。人間の生体リズムと自然光との関係性を明らかにし、病院から自宅まで活用できる技術を構築するために、時間ごとの色温度や照度、1日の変化のパターン、そのために必要な照明システムなど、多方面にわたり研究を進めてきた。また、光源の波長を制御できるLEDの発達により、省エネとの両立も可能になった。京都大学医学部附属病院南病棟は、その成果をLEDによって大規模に実現した初めての事例となった。ホスピタルサーカディアンシステムの基本となる研究成果は、医療分野の専門家の力を借りて2000年にまとめられた冊子「光と健康」で見ることができる。


今回、導入された「ホスピタルサーカディアンシステム」はベッドサイドの壁面照明(アッパーライト)と天井のスクエアベース照明の2種類の照明器具で構成され、調光・調色が可能なシステムとなっている。アッパーライトは標準品のブラケットのデザインはそのままで、内部のユニットや電源はスクエアベース用につくられた調光・調色可能な部品を組み込んでおり、自然光と同調するように自動で変化する。そのスケジュールはスタッフステーションに設置した「マルチマネージャー(照明制御装置)」によって、自動的に1日の照明制御シ ーンを再現する。また、ブラケットの読書灯機能や天井に取り付けたユニバーサルダウンライト(処置灯)はシステムと独立して必要な時に点灯可能となっている。

特注のLED病室ベッドライト(調光調色)
LEDスクエアベースライト(調光調色)
マルチマネージャー
設定用タブレット