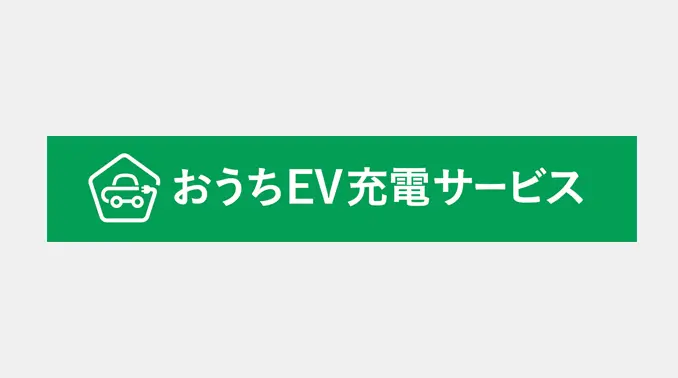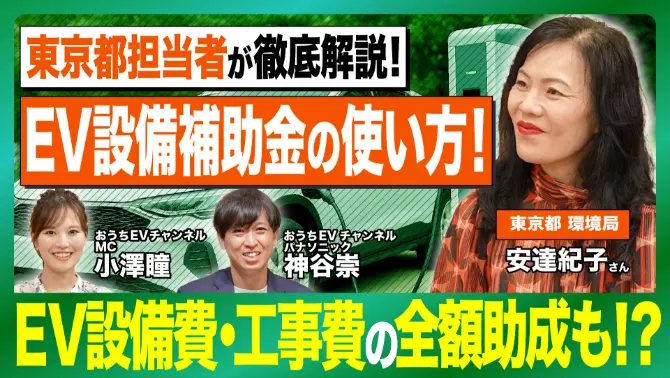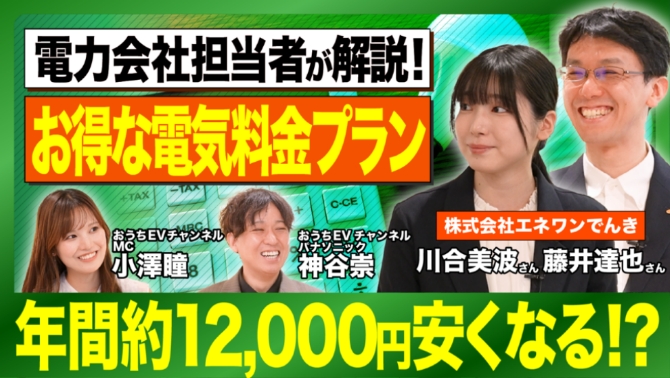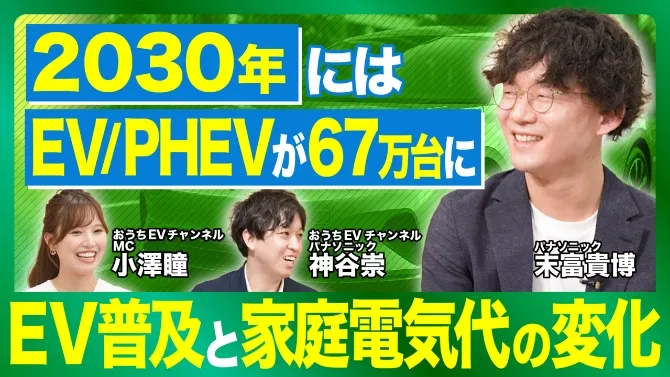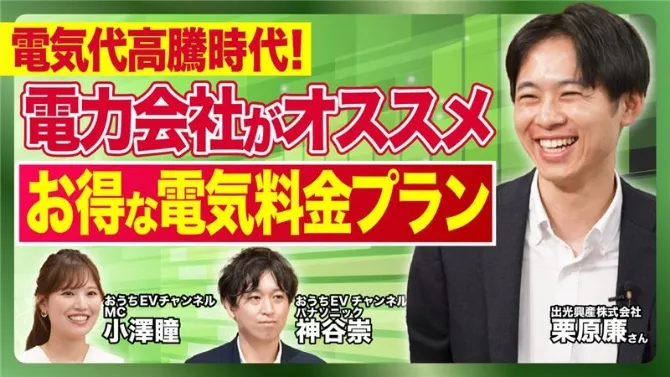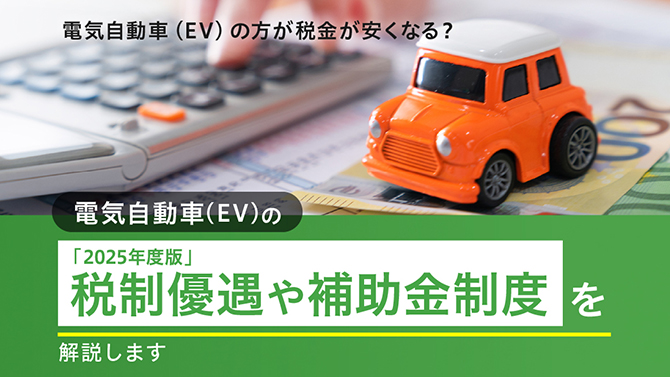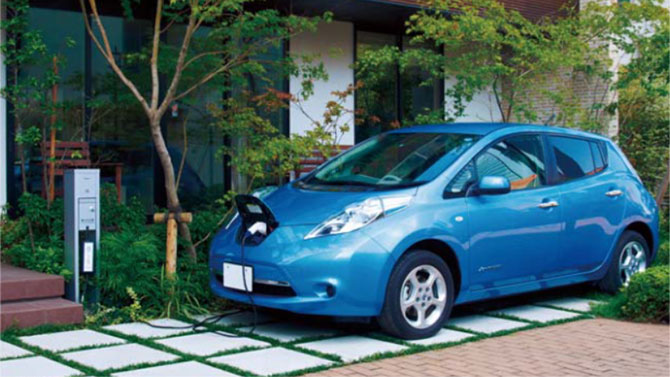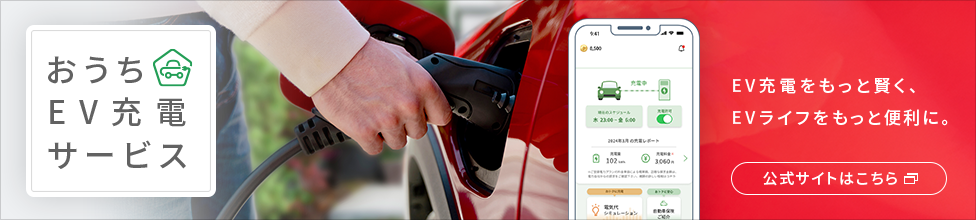電気自動車(EV)のメリットとデメリットについて解説


近年、燃料などの維持費を抑えられるという理由から、電気自動車(EV)に注目が集まっています。電気自動車(EV)はバッテリーやモーターなどを用い、電気を動力として走る車のことです。本記事では、どのようなメリット、デメリットがあるのかについて解説します。
電気自動車(EV)とは
電気自動車(EV)の定義を説明した上で、代表的な車種を紹介します。
電気自動車(EV)の定義
電気自動車(EV)は、英語で「Electric Vehicle」と表します。その意味は「電気エネルギーで走行する車両」です。一般的に電気自動車(EV)という言葉が使用される場合、BEV、HEV、PHEV、FCEVがあり、そのうちBEVのみを指すこともあります。
ただし、BEVのみが電気自動車(EV)ではないため、電動化された自動車は電動車「xEV」と表記され、次のように大きくわけられています。
| BEV (Battery Electric Vehicle) |
バッテリーに充電した電気を使い、モーターを駆動させる電気自動車 |
| HEV (Hybrid Electric Vehicle) |
エンジンとモーターという2つの動力源を持っているハイブリッド車 |
| PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) |
HEVに自宅や外出先の電源から充電できる機能を備えたプラグインハイブリッド車 |
| FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle) |
燃料の水素を空気中の酸素と化学反応させて発電し、モーターを駆動させる燃料電池車 |
電気自動車(EV)の詳細はこちらから
<参考>
- 「電気自動車のしくみ(森本雅之監修)」(ナツメ社/2024年5月13日発行)P12~15
- 「電気自動車(EV)だけじゃない?「xEV」で自動車の新時代を考える」(経済産業省)
- 「次世代自動車ガイドブック2018-2019」(環境省・経済産業省・国土交通省)
電気自動車(EV)のメリット
ここからは、電気自動車(EV)が従来のガソリン車と比較して「どのようなメリットがあるのか」を説明します。
1. ゼロエミッションで走れる
電気自動車(EV)には、エンジンがありません。ガソリンなどの化石燃料を燃やさないため、電気自動車(EV)は走行中にCO2などの排気ガスを排出しません。できる限りCO2を出さずに0(ゼロ)に近づけるという「ゼロエミッション」を目指して走行できます。排気ガスは大気汚染や気候温暖化の原因となるので、電気自動車(EV)を利用することにより環境的メリットがあります。
2. 振動や騒音が少ない
電気自動車(EV)の動力源はモーターです。モーターの作動は、振動と騒音が非常に小さいことが特長です。一方、ガソリン車は車体の内部で燃料を爆発させているため、振動が大きく、騒音も大きくなります。そのため、電気自動車(EV)はガソリン車よりも静かに、かつスムーズに走ることができます。
3. 維持費を抑えられる
電気自動車(EV)は、ガソリン車より維持費を安く抑えられます。理由は、主に2つです。1つはガソリン車と違い、エンジン・オイルなど定期的に交換が必要なエンジンに関するメンテナンス費用がかかりません。また、もう1つは自宅に充電設備があれば電気代の安い時間帯に電気を充電できるため、ガソリン代より安く抑えることができます。
4. 蓄電池として利用できる
電気自動車(EV)には、大容量のバッテリーを搭載しています。例えば、バッテリーに蓄えられている電気は、V2Hを用いることで自宅に供給することが可能です。つまり、V2Hがあれば、電気自動車(EV)は蓄電池として利用できます。電気代の安価な時間帯に電気自動車(EV)に充電し、電気代の高い時間帯に蓄えた電気を自宅で使えば電気代を削減することができます。
5. 対象車両はCEV補助金が受けられる
電気自動車(EV)には、補助金が用意されています。国による補助金だけでなく、自治体ごとにも補助金を用意している場合もあります。また、車両そのものに対する補助金だけでなく、充電設備にも補助金があります。V2H充放電設備、外部給電器、水素供給設備などがあるため、次世代自動車振興センターのホームページをチェックすることをおすすめします。
6. 自宅で充電できる
自宅に充電設備を設置した場合、ガソリン車のようにガソリンスタンドに行く手間などなく、電気自動車(EV)に電気を補給することが可能です。電気自動車(EV)に自在に電気を補給できるため、安い電気料金プランに変更したり電気代が安い深夜帯を利用したりすれば、自宅の電気代を抑えることもできます。
電気自動車(EV)の自宅充電についてはこちらから
電気自動車(EV)の
デメリット
電気自動車(EV)にはメリットだけでなく、デメリットもあります。電気自動車(EV)の購入を検討している方は理解しておきましょう。
1. 車両価格が高い
電気自動車(EV)は、車両価格がガソリン車よりも割高になっています。それぞれの自動車メーカーで同じクラスのガソリン車と電気自動車(EV)とを比較すると、車両価格は1.5倍から数倍という差が生じている傾向があります。その理由は、電気自動車(EV)に搭載される駆動用のバッテリーが高額であることが挙げられます。
2. 航続距離が短いものもある
電気自動車(EV)の航続距離は、バッテリーの容量次第です。大容量のバッテリーを搭載する車種は航続距離が長くなります。市販されている電気自動車(EV)のほとんどが、同クラスのガソリン車の航続距離には及びません。長期休暇での家族旅行など遠方に移動する場合、ガソリン車は無給油で目的地にたどり着けても、電気自動車(EV)は途中充電が必要になる場合が多いのが現状です。
3. 充電に時間がかかる
電気自動車(EV)の充電には、時間がかかります。電気自動車(EV)のバッテリー容量によって異なりますが、普通充電の場合、満充電には12~24時間程度かかります。急速充電を使用した場合でも、満充電には30分以上の時間がかかります。ガソリン車の給油が数分で済むことを考えると、電気自動車(EV)は事前に充電しておくなど計画的な利用を心がけることが大事です。
4. 充電設備が必要になる
現状、電気自動車(EV)の充電には時間がかかることを考えると、外充電のみで済ませることは現実的ではありません。当社調べでは、持ち家や戸建てに住んでいる3年以内の電気自動車(EV)購入者は、97%が自宅に充電設備を設置しています。また、電気自動車(EV)を充電する場所に関する調査では、86%が自宅で充電しています。そのため、おうち充電は基本路線であり、充電設備を整備することが必要です。
電気自動車(EV)の充電にかかる電気代の詳細はこちらから
補助金を利用すれば
解決できる課題もある
電気自動車(EV)のデメリットとして取り上げた2つの課題については、補助金を利用することで解決することが可能です。
車両価格について
現状の電気自動車(EV)は駆動用バッテリーが高価であるため、車両価格がガソリン車よりも割高になってしまいます。そこで、国や自治体は電気自動車(EV)の購入に対して補助金を用意しています。
CEV補助金を利用する
国が用意している電気自動車(EV)などに対する補助金は「CEV(クリーン・エネルギー・ビークル)補助金」です。現状国内で販売されているほとんどの電気自動車(EV)が対象になっており、1台あたり最大85万円の補助金が支給されます。
ただし、中古車および事業用車両はCEV補助金の対象外なので注意しましょう。この補助金を利用する場合は、一般社団法人次世代自動車振興センターに申請します。
充電設備について
電気自動車(EV)は、基本的におうち充電を行います。そのため、自宅に充電設備を設置する必要があり、初期費用と初期工事がかかります。充電設備については、国や自治体が補助金を用意している場合があります。地域によって補助金の有無や内容が異なりますので、導入前に確認してみましょう。
V2H充放電設備補助金を利用する
V2H充放電設備を設置する方に向けて用意された補助金が、V2H充放電設備・外部給電器補助金です。個人宅も対象になります。令和5年度補正予算・令和6年度当初予算では、設備費が上限30万円として機器購入費の3分の1、工事費は上限15万円です。購入するV2Hのモデルによって助成額は異なりますが、合計で最大45万円の補助金を利用できる可能性があります。
なお、V2Hとは「Vehicle to Home」の略称で、日本語に訳すと「車から家へ」という意味です。V2Hを通して電気自動車(EV)と自宅との双方向に送電できるため、バッテリーを蓄電池としても利用できます。
充電設備補助金を利用する
CEV補助金と同様に、一般社団法人次世代自動車振興センターが受け付けるのが、充電設備補助金です。マンション、月極駐車場および工場などが対象です。個人宅の駐車場は対象外となります。
電気自動車(EV)の補助金の詳細はこちらから