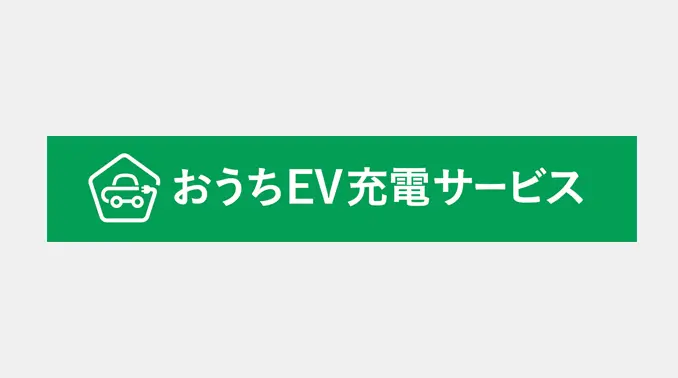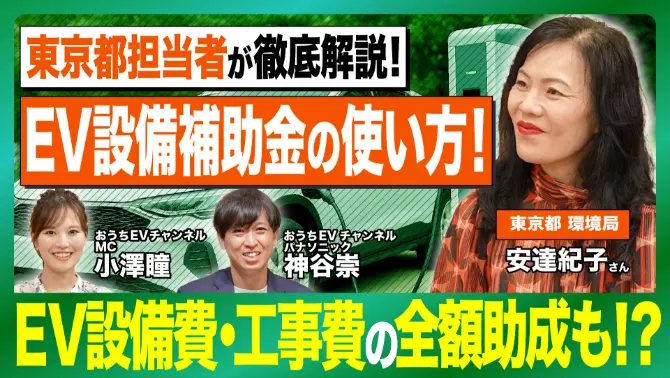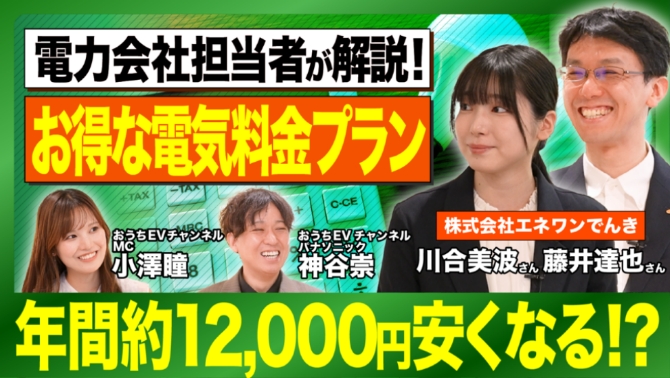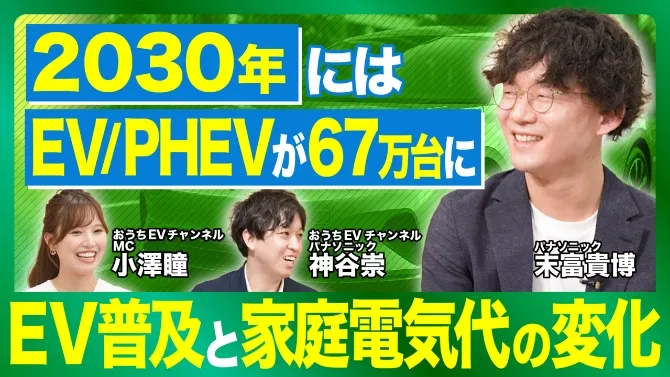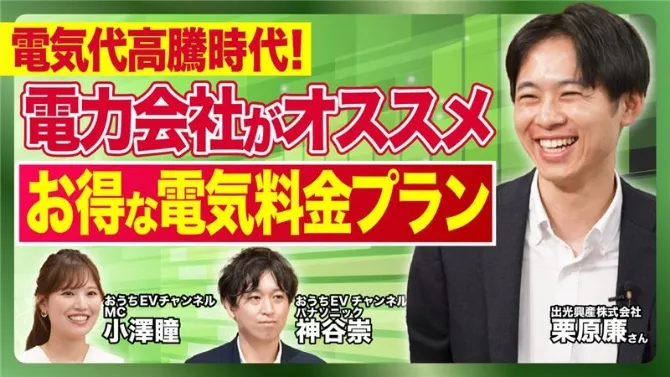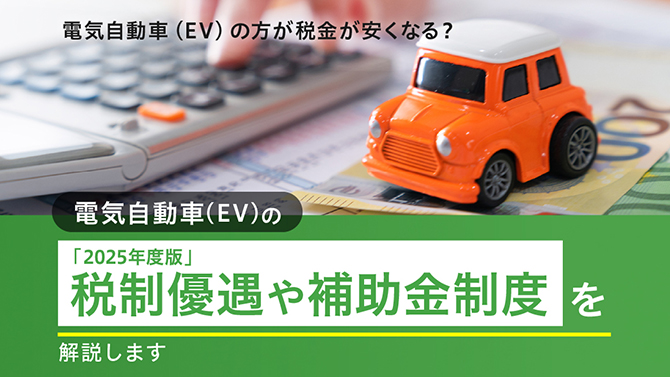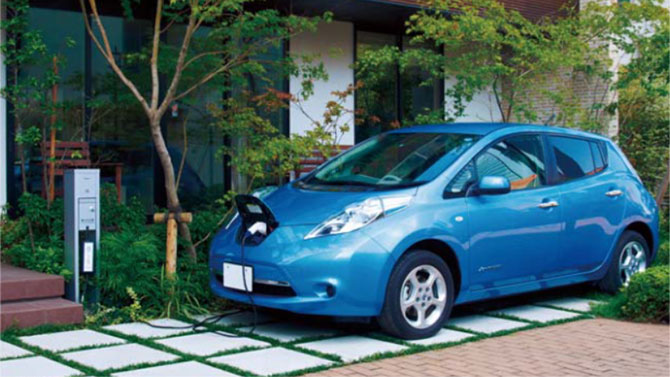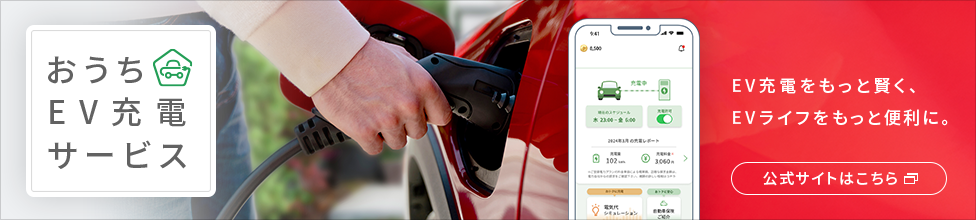電気自動車(EV)と充電設備の補助金とは?国や自治体の制度、注意点を解説


走行中にCO2などの排気ガスを減らすことができ、地球環境に配慮した電気自動車(EV)。近年は普及が進んでいますが、ガソリン車より車両価格が割高などの課題があります。そこで、国や自治体は電気自動車(EV)の普及促進のため、補助金を交付しています。
本記事では、電気自動車(EV)と充電設備に関わる補助金の基礎知識や申請時の注意点、交付までの流れについて解説します。
電気自動車(EV)と
充電設備の導入は初期費用が高いため、
国や自治体が
補助金を交付している
電気自動車(EV)はガソリン車に比べると、初期費用の負担が多い傾向にあります。まず、車両価格がガソリン車より割高であることがほとんどです。また、電気自動車(EV)を購入する場合は自宅に充電設備を設置する必要があります。
電気自動車(EV)のメリットとデメリットの詳細はこちらから
そのため、国や自治体は初期費用の負担を軽減しようと、さまざまな補助金を交付して電気自動車(EV)の普及・推進を後押ししています。
電気自動車(EV)に関わる
補助金の基礎知識
電気自動車(EV)と充電設備の導入については、国や自治体が補助金を用意しています。国や各自治体によって内容は異なりますが、どのような補助金があるのでしょうか。ここでは、電気自動車(EV)に関する補助金の目的や種類、概要などについて紹介します。
補助金の目的
電気自動車(EV)や充電設備に対して補助金を交付する背景には、国が掲げる2050年までのカーボンニュートラル実現に向けた動きがあります。カーボンニュートラル実現には、CO2をはじめとする温室効果ガスの排出量を大きく減らすことが必要です。そのため、現在さまざまな分野で脱炭素に向けた取り組みが進められています。
自動車業界も連外ではなく、国は「乗用車は、2035年までに、新車販売で電動車100%を実現」という目標を掲げ、クリーンエネルギーの導入に力を入れています。この電動車には電気自動車(EV)のほか、プラグインハイブリッド車(PHEV)やハイブリッド車(HEV)、燃料電池自動車(FCV)が含まれています。
電気自動車(EV)の詳細はこちらから
ガソリン車に比べて走行中にCO2などの排出量を減らすことが可能で、地球環境に配慮したメリットがあります。つまり、電気自動車(EV)に関連した補助金は、脱ガソリン車を加速させ、温室効果ガスの排出量を削減することが大きな目的です。
補助金の種類
電気自動車(EV)に関連する補助金は、国から交付される補助金と自治体から交付される補助金の2つがあります。補助金の内容は国やそれぞれの自治体によって異なります。電気自動車(EV)自体の車両購入に利用できる補助金や、充電設備に利用できる補助金などいくつか種類があります。
ここでは、国の補助金と自治体の補助金で、それぞれ実際に交付されている補助金について概要を説明します。
国から交付される補助金
電気自動車(EV)や充電設備に利用できる国の補助金は、主に4つあります。それぞれの補助金について、概要や上限金額などを紹介します。
1. CEV補助金
CEV補助金の正式名称は「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」で、CEVは「Clean Energy Vehicle」の略称です。CEV補助金は、電気自動車(EV)などを導入する際に対象車両に補助金を交付しています。対象車両は電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)などです。
利用対象者は個人のほか、法人や地方公共団体、リース企業です。具体的な補助金額はメーカーや車種によって異なりますが、令和6年度の場合、電気自動車(EV)が最大85万円、軽の電気自動車(軽EV)が最大55万円、プラグインハイブリッド車(PHEV)が最大55万円、燃料電池自動車(FCV)が最大255万円となっています。
2. V2H充放電設備・外部給電器補助金
この補助金は、その名の通りV2H充放電設備と外部給電器を導入する際に利用できる補助金です。V2Hは「Vehicle to Home」の略称で、設置すると電気自動車(EV)を充電できるだけでなく、電気自動車(EV)の電気を自宅でも利用できるようになります。
外部給電器は電気自動車(EV)の電気を取り出して、自宅の電化製品を使えるように変換できる機器です。つまり、外部給電器は電気自動車(EV)の電気を持ち運んで蓄電池のように利用できる機器です。
どちらの補助金も対象者は個人をはじめ、法人や地方公共団体、リース企業です。どちらの補助金も充電設備の機器本体に対して適用されますが、V2H充放電設備については設置工事も補助対象です。V2H充放電設備の補助金額は機器本体がどのモデルか、また設置場所が公共施設か災害拠点かによっても変わります。
V2H充放電設備に関する補助金の上限は機器本体が75万円、設置工事費は設置場所が公共施設や災害拠点なら最大95万円、それ以外は最大15万円です。また、外部給電器の補助金は上限が50万円です。
3. ZEH補助金
ZEH補助金は住宅向けの補助金です。 ZEHは「Net Zero Energy House」の略称で、「エネルギー収支をゼロ以下にする家」という意味です。直接的に電気自動車関連の補助金ではありませんが、充電設備が補助対象となっています。
ZEH補助金の要件として、電気自動車(EV)の充電設備とV2H充放電設備が追加補助の対象設備になっており、新築住宅の設置時に限り補助を受けられます。上限は20万円となっており、ZEH+のハイグレード仕様として追加条件を満たすと、さらに追加で補助金を受け取ることも可能です。
ZEHのコンセプトは高断熱かつ高気密な住宅でエネルギー消費を抑えつつ、太陽光発電などでつくったエネルギーで消費エネルギーをまかなうことです。ZEH補助金は、建築業界が実施する地球環境対策の一環です。
電気自動車(EV)の自宅充電についてはこちらから
4. 充電設備補助金
充電設備補助金は、電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)の充電設備を導入する際に利用できる補助金です。正式名称は「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」といいます。
個人は対象外で、事業者向けの補助金です。具体的には、高速道路のSAやPA、道の駅に設置する場合、もしくはマンションや月極駐車場、事務所・工場に設置する場合が補助対象となります。この補助金は、充電設備本体の購入費に加えて、設置工事費用も補助対象です。
充電設備は購入費の2分の1から全額、設置工事費用は全額が補助されます。実際の補助金額は導入する充電設備や設置場所によって条件がありますが、高速道路だと3,700万円、商業施設などであれば880万円が上限となっています。
自治体から交付される補助金
電気自動車(EV)の補助金は、自治体からも交付されている場合があります。ただし、補助対象や補助金額、利用対象者などの要件はそれぞれの自治体によって異なります。
すぐ探せる!! 補助金検索(市町村・商品別)の詳細はこちらから
ここでは、東京都を取り上げ、自治体補助金の参考例として紹介します。
補助金・助成金(クール・ネット東京)の詳細はこちらから
東京都の場合
東京都も電気自動車(EV)に関連する補助金を交付しています。ここでは、2つの補助金について紹介します。
・燃料電池自動車等の普及促進事業・電気自動車等の普及促進事業
CO2の削減を図ることを目的に、電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)の導入を後押しするための補助金事業です。補助金交付については車両本体に加えて、V2H充放電設備と外部給電器も補助対象になっています。

補助金の利用対象者は、都内に住む個人や都内に事業所を構える法人、市区町村、リース企業です。補助金額は給電機能の有無によって異なり、ある車両は45万円、ない車両は35万円となっています。設備関連については上乗せ助成金額で、V2H充放電設備と外部給電器とも一律で10万円と定められています。
・【令和6年度】戸建住宅向け充電設備普及促進事業
この事業では、戸建て住宅向けに電気自動車(EV)関連の充電設備導入を後押しするために補助金を交付しています。東京都内の既築の戸建て住宅に電気自動車(EV)の充電設備を設置する方が対象者で、新築の戸建て住宅への設置は対象外です。
補助金額は充電設備に通信機能があるかどうかで変わります。通信機能がある場合は、充電設備1基あたり上限30万円、それ以外は1基あたり2.5万円が補助されます。
<参考>
- 「カーボンニュートラルとは」(環境省)
- 「自動車・蓄電池産業」(経済産業省)
- 「クリーンエネルギー自動車の購入補助金がリニューアル、自動車分野のGXをめざせ」(経済産業省)
- 「令和4年度補正予算・令和5年度当初予算『クリーンエネルギー自動車導入促進補助金』、『クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金』」(経済産業省)
- 「(別表1)銘柄ごとの補助金交付額」(一般社団法人次世代自動車振興センター)
- 「充電インフラ整備に向けた取組の強化」(経済産業省)
- 「別表1-2事業ごとの設置工事に係る補助金交付上限額」(一般社団法人次世代自動車振興センター)
- 「『V2H充放電設備/外部給電器』の導入補助金の概要(令和5年度補正・令和6年度当初)」(経済産業省)
- 「2024年の経済産業省と環境省のZEH補助金について」(一般社団法人 環境共創イニシアチブ)
- 「令和6年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金「(一般社団法人 環境共創イニシアチブ)
- 「全国の地方自治体の補助制度・融資制度・税制特例措置」(一般社団法人次世代自動車振興センター)
- 「FCV・EV・PHEV車両(燃料電池自動車等の普及促進事業・電気自動車等の普及促進事業)」(東京都地球温暖化防止活動推進センター)
- 「【令和6年度】戸建住宅向け充電設備普及促進事業」(東京都地球温暖化防止活動推進センター)
補助金を申請する際の注意点
電気自動車(EV)に関連する補助金を申請する際の注意点について紹介します。自治体の補助金は交付の有無がそれぞれ異なるため、ここでは、主に国の補助金を利用する際の注意点を取り上げます。
交付条件や金額は毎年変わる
補助金の交付条件や金額については、毎年変更される可能性があります。過去には、交付条件が一部変更されたこともあります。補助金の内容については、実際に公募が始まらないと詳細がわからないため、電気自動車関連の補助金を検討している場合は、早い段階からこまめにホームページで最新情報をチェックしましょう。
予算がなくなり次第、受付終了
電気自動車関連の補助金は予算がなくなったタイミングで、受付が終了となります。たとえ補助金申請の受付期間内であっても、予算に到達した段階で受付が終了となったことが過去にあります。そのため、電気自動車関連の補助金を検討する場合はできるだけ早く申請するため、早めに計画を立てることをおすすめします。
対象外となる電気自動車(EV)もある
補助金の対象外となる電気自動車(EV)があることも、注意点の1つです。対象となる電気自動車(EV)はそれぞれ補助金によってメーカーや車種が指定されており、すべての車両が補助金の対象ではありません。
「補助金を利用して電気自動車(EV)を購入しよう」と検討している場合は、事前に補助金の対象なのかチェックする必要があります。補助対象となる電気自動車(EV)も、各年によって変更される場合があるので注意しましょう。
補助金の交付申請書の提出期限
補助金申請には、提出期限があります。一例として「令和5年度補正予算 CEV補助金」を取り上げます。
まず、原則として交付申請書の提出期限は「車両の初度登録(届出)の日から1か月以内」と定められています。具体的には、翌月の前日までの消印が有効です。電気自動車(EV)などの購入日や契約日が起点ではない点、提出期限が車両の初度登録の日から1か月以内とあまり時間がない点に注意が必要です。
なお、例外として支払い手続きの関係などで車両登録日までに車両代金支払い、または全額支払いが完了しない場合に限り、1か月の猶予が与えられます。その場合は、翌々月の末日までの消印が提出期限となります。
自治体によっては補助金がない
自治体に関しては、電気自動車関連の補助金を交付していない場合があります。前年度は補助金を交付していても、翌年度に取り止める場合があります。逆に、新たに補助金事業を始める自治体もあるため、自治体のホームページもこまめにチェックすることをおすすめします。
補助金交付の条件
補助金の交付には、満たさなければならない条件が定められています。ここでは、主な条件として3つ紹介します。
補助金対象車両、かつ自家用自動車に限る
補助金交付の条件として、補助金対象車両であり、かつ自家用自動車に限られる点があります。補助金対象の車両であったとしても、事業者用自動車として登録すると補助対象外です。補助金対象の車両については、次世代自動車振興センターのホームページにまとめられているので確認しましょう。
国が実施する他の補助金と重複できない
国の補助金は、2つ重複して申請ができません。つまり、国の補助金は1種類のみ利用が可能です。そのため、複数の補助金を検討している場合は条件が合致した中で、どれを選ぶのかを吟味する必要があります。なお、国の補助金と自治体の補助金については併用できる場合もあるため、それぞれのホームページをしっかりチェックしましょう。
補助金を使った購入車両は3年もしくは4年の保有義務がある
見落としがちな条件が、補助金を利用して購入した電気自動車(EV)の3年もしくは4年間の保有義務です。補助金の交付を受けた車両は取得財産になるため、この期間中に乗り換えや売却などで購入車両を手放すと、補助金の全額返納または一部返納を求められる可能性があります。なお、何らかの理由でやむを得ず購入車両を処分する場合は、所定の手続きが必要です。詳しくはホームページをしっかり確認した上で、手続きを進めましょう。
補助金申請から
交付までの流れ
ここからは、補助金を申請してから実際に交付されるまでの流れについて説明します。自治体の補助金については交付していない場合もあるため、国の補助金を例に取り上げます。
CEV補助金
CEV補助金の補助金申請から交付までの大まかな流れは次の通りです。それぞれのステップについて、簡単に見ていきましょう。
- 登録届出
- 申請書類提出
- 審査
- 補助額決定
- 補助金交付
- 車両の保有
1. 登録届出
補助金を利用して対象車両を購入した場合は、登録届出を行います。登録届出については、電気自動車(EV)を購入したディーラーが手続きする場合が多いです。補助金交付申請書類を提出する前に、登録(軽自動車等は届出)と車両代金の支払いは完了させておく必要があります。
2. 申請書類提出
補助金交付申請書類に必要事項を記入して、CEV補助金を管轄する次世代自動車振興センターへ提出します。申請書類の提出は、郵便か宅配便かの方法で指定されています。なお、次世代自動車振興センターへの直接持ち込みによる提出は受け付けていないので注意しましょう。
3. 審査
提出された補助金交付申請書類は不備がないか、補助金対象となる条件を満たしているかなどを審査されます。審査には、1か月から2か月ほどかかることが多いようです。なお、審査状況は次世代自動車振興センターのホームページでも確認できます。
4. 補助額決定
審査後、申請内容に問題がなければ補助金交付の条件に則って補助額が決定されます。
5. 補助金交付
補助金交付が決まったら、次世代自動車振興センターから交付決定兼確定通知書によって補助金が通知されます。その後、補助金が指定口座に振り込まれるのは、交付決定兼確定通知書が発行されてから1週間程度かかるようです。
6. 車両の保有
CEV補助金は、補助金が交付されたら完了ではありません。補助金交付を受けた車両は取得財産扱いのため、3年または4年間保有する義務が発生します。その期間内に車両を処分すると、補助金の全額または一部を返納する必要があるので注意しましょう。
V2H充放電設備・外部給電器補助金
充電設備補助金、V2H充放電設備・外部給電器補助金の補助金申請から交付までの主な流れは、次の通りです。
- 申請書類提出
- 審査
- 補助額決定
- 設置工事
- 実績報告
- 補助金交付
1. 申請書類提出
まずは、補助金交付に必要な申請書類を提出します。申請書類は補助金の種類によって異なるため、提出前に確認しましょう。充電設備補助金、V2H充放電設備・外部給電器補助金の補助金申請はオンラインのみです。また、補助金申請を行う前の発注、設置後の申請は補助対象外になるので注意しましょう。
2. 審査
申請を行うと次世代自動車振興センターで審査が行われます。審査には、1か月から2か月ほどの期間がかかることが多いようです。
3. 補助額決定
審査後、申請が承認されたらその内容に応じて補助金額が決定します。審査結果と補助金額は、交付決定通知書にて通知されます。
4. 設置工事
交付決定後に、充電設備の発注や設置工事を進めることが可能です。
5. 実績報告
充電設備の設置工事や支払いが完了したら、オンラインで実績報告を申請します。
6. 補助金交付
実績報告後、あらためて審査が行われ、最終的な補助金額が確定します。確定通知書が送付され、指定の金融機関の口座に振り込みが行われます。実績報告してから実際に補助金が振り込まれるまでは、およそ1.5か月から2か月程度かかることが多いようです。