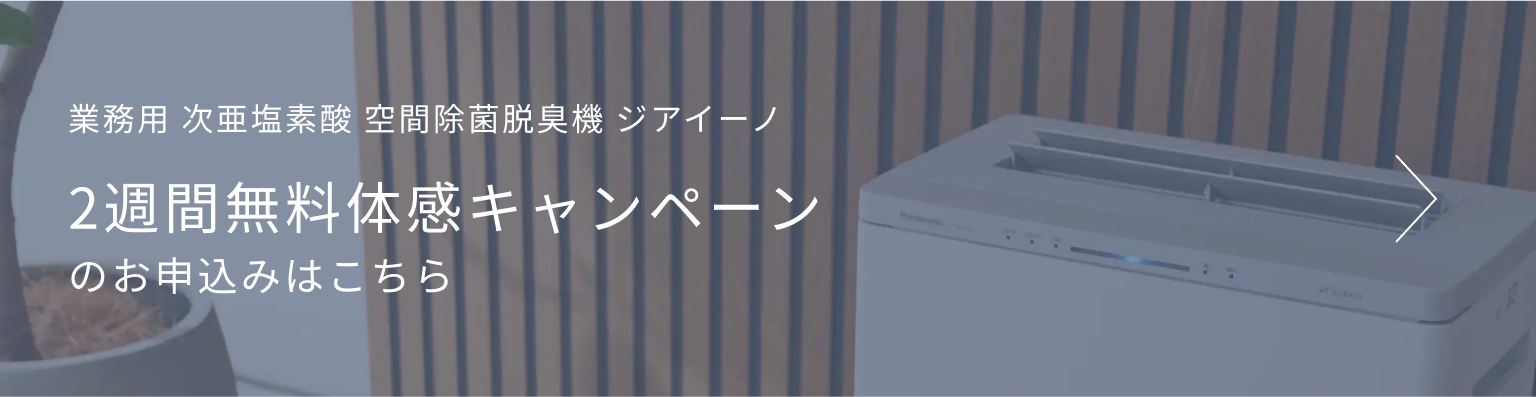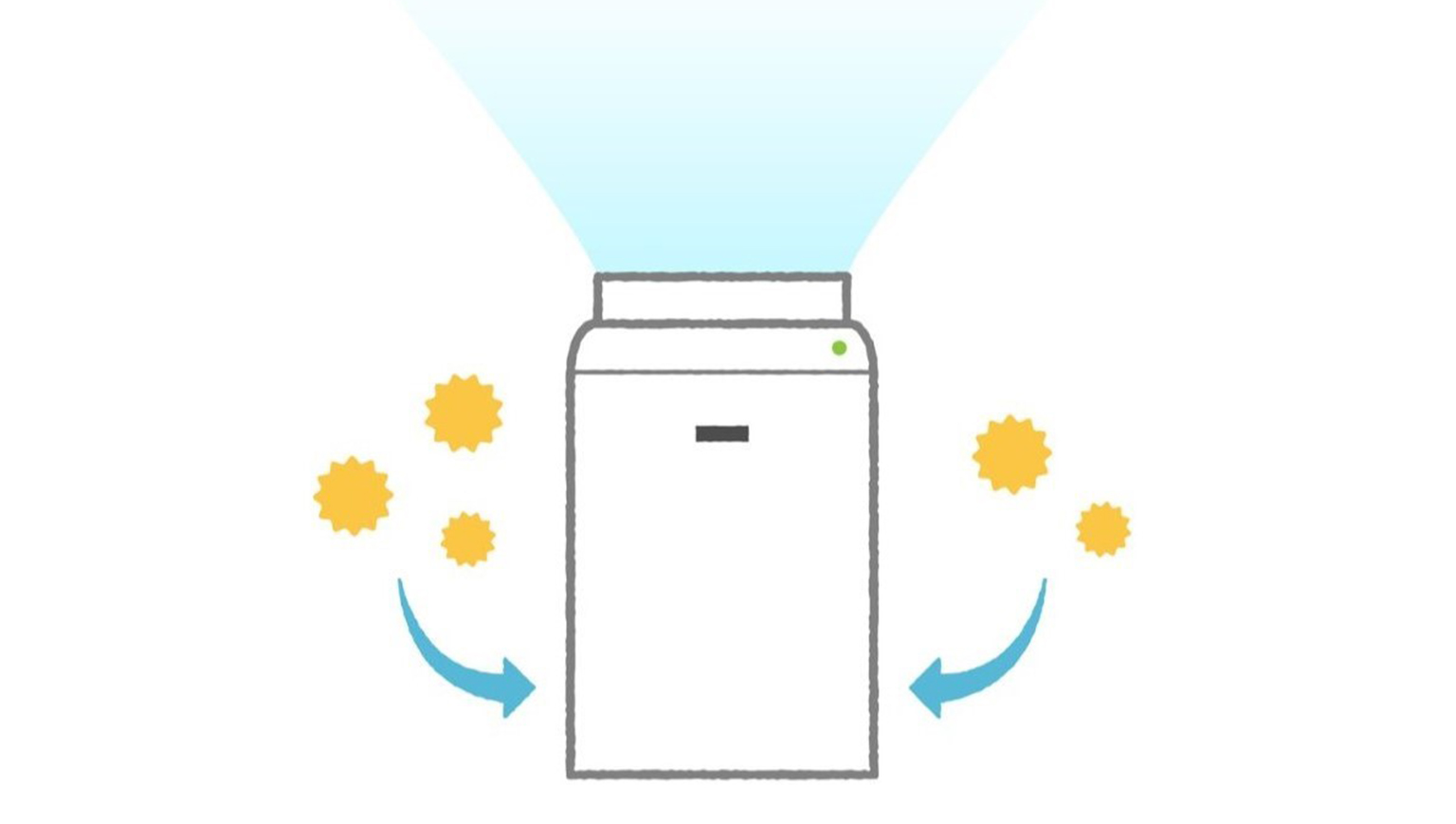犬の臭い(ニオイ)対策はどうする?原因や具体策、部屋のニオイを減らす方法

ペットショップや動物病院、トリミングサロン、ペットホテルなどには多くの犬が集まります。一般的な家庭と比べるとニオイが強くなりやすいため、対策にお困りの方も多いのではないでしょうか。犬のニオイが気になるときは、犬の体のケアを行うことに加え、空気そのものの質を改善するなど、空間に対するニオイ対策も大切です。
この記事では、犬のニオイの主な原因や対策方法についてご紹介します。犬のニオイ対策にお悩みの事業者様は、ぜひ参考にご覧ください。
目次
犬の臭い(ニオイ)の主な原因は?
犬のニオイの原因としてよく挙げられるのが、汗などの分泌物や口臭、排泄物などです。それぞれ適切な対応をせずに放置してしまうと、部屋の空間全体にニオイが染み付いてしまう可能性があります。こちらでは犬のニオイの原因について詳しく解説します。
アポクリン腺が全身にあるため
犬の体臭が強くなりやすいのは、全身にアポクリン腺という汗腺があるためです。
アポクリン腺は皮脂腺につながっていることが特徴で、皮脂を含んでじっとりとした汗を分泌します。この汗に含まれている皮脂が酸化すると、雑菌が繁殖して強い体臭の原因になります。
人間の場合は、脇の下や乳輪、耳の中など、体の一部にしかないのですが、犬は全身にアポクリン腺があるため、強いニオイを発生しやすくなっています。
また比較的ニオイが少なく、体温調節のためにかくサラっとした汗はエクリン腺から分泌されるのですが、人間は全身にエクリン腺がある一方、犬は肉球にしかありません。
このような汗腺の特徴が、犬のニオイの原因になっています。
歯周病にかかりやすいため
犬は歯周病になりやすいという特徴があります。歯周病になると口臭が強くなり、ニオイの元になります。原因は口の中の唾液が関係しています。人間の唾液が弱酸性~中性なのに対し、犬の唾液はアルカリ性です。歯周病菌は酸性よりもアルカリ性の環境のほうが活動しやすくなっており、歯周病の原因となる歯石が形成されるまでの速度に大きな違いがあります。具体的には、食べかすが歯垢になり、歯に付着した歯垢が歯石になるまでの日数は、人間では約25日間、犬では約3日間と8倍も違います。このように、口の中の性質の違いによって繫殖しやすい細菌は異なり、アルカリ性の犬では歯周病菌が増殖しやすくなります。
排泄物のニオイが強烈なため
犬のうんちやおしっこ、おならのニオイの原因は、アンモニアや消化しきれていない食べ物、腸内細菌の働きによって発生するガスなどです。そもそも排泄物のニオイは気になるものですが、腸内環境が悪化していると、さらにニオイが強烈になってしまうケースがあります。
フードやおやつをあげすぎていたり、体質に合っていない食事を与えていたりすると、腸内環境の悪化につながります。また、運動不足をはじめとするストレスも不調を招き、胃腸へ影響を及ぼす可能性があります。
犬の臭い(ニオイ)対策は?
ご紹介した通り、犬のニオイは汗や口臭、排泄物などさまざまな原因があります。こちらでは、主なニオイ対策の方法をご紹介します。
体を清潔な状態に保つ
犬のニオイを防ぐためには、月に1~2回の頻度でシャンプーをすることが望ましいでしょう。皮脂や汚れを洗い流すことで、ニオイを軽減できます。犬の体質によって適切なシャンプーの頻度は異なりますが、乾燥しやすい冬場は3~4週に1回、湿気が多い夏場は2~3週に1回程度が目安です。
シャンプーをした後は泡が残らないようによくすすぎ、ドライヤーで十分に乾かしましょう。洗い残しや生乾きは雑菌が繁殖する原因となり、ニオイの元になる可能性があります。フレンチ・ブルドッグやパグなど、シワの多い犬種はウェットシートや綿棒を使ってシワの間を掃除してあげると良いでしょう。
雨の日の散歩後は濡れたままにしない
雨の日の散歩から帰ってきたら、全身をしっかりと乾かしてあげましょう。被毛や皮膚を濡れたまま放置すると雑菌が繁殖し、ニオイの原因になります。また、外耳炎を招いてしまい、強いニオイを発することがあるため、耳の中の水分も優しく拭き取りましょう。
タオルで全身を拭き取ったら、ドライヤーをかけて完全に乾かします。足やお腹などが泥だらけになってしまっている場合は、部分的にシャンプーをしても良いでしょう。
毎日歯磨きをする
口臭ケアのために、歯磨きは毎日行いましょう。磨き残しを防ぐためには、犬用歯ブラシで磨くのが望ましいですが、歯ブラシが苦手な犬も少なくありません。デンタルスプレーや歯磨きシートなどを活用しながら徐々に慣れさせていきましょう。
毎日の歯磨きによって歯石ができるのを防ぐことで、歯周病予防にもつながります。歯周病は歯だけでなく、他の病気を誘発することもあります。また、歯石除去の歯科治療が必要になった際は全身麻酔が必要になることもあります。犬の健康のためにも、日頃から欠かさず歯を磨いてあげることが大切です。
ブラッシングを行う
1日に1回はブラッシングを行い、体を清潔に保ちましょう。ブラシをかけることで、抜け毛や被毛に付いたニオイの原因となる汚れを取り除けます。
また、普段のお手入れではペット用ウェットシートや蒸しタオルなどで全身を拭いてあげることがおすすめです。顔周りは目やにやよだれ、食べかすが付着しやすいため、こまめに拭き取りましょう。お腹周りや足の裏、おしり周りも丁寧に拭きます。
さらに、耳の汚れのチェックを週1回程度行い、汚れがあれば軽く拭いてあげることも大切です。外耳炎になると濃い黄色や茶色の耳垢が増え、強いニオイを発するようになってしまいます。外耳炎を予防するためにも、週1回の汚れのチェックに加え、月に1~2回を目安にイヤークリーナーを使用した耳掃除をするようにしましょう。
部屋に犬の臭い(ニオイ)が付くのを防ぐには?
日頃のお手入れでケアをしてあげるのと同時に、室内にニオイが染み付いてしまう前に空間のニオイ対策もすることがおすすめです。ここでは、部屋に犬のニオイを付けないためのポイントをご紹介します。
こまめに換気を行う
部屋はニオイがこもりやすいため、こまめに換気を行って臭気を外に逃がすことがポイントです。窓を開けたり、換気扇を付けたりして空気を入れ換えましょう。風通しが悪い部屋はサーキュレーターを活用することもおすすめです。
消臭剤や消臭スプレーを使用する
消臭効果のあるアイテムを活用することで、気になるニオイを軽減できることがあります。一般的な消臭剤や消臭スプレーではなく、なるべくペット用として製造されたものを使用しましょう。スプレーをかけた箇所を犬が舐めてしまうことがあるため、犬にとって安全な成分で作られたものを使うことがおすすめです。
布製品や犬のベッドは念入りに清掃する
カーペットやカーテンなどの布製品には犬の体臭が蓄積しやすいため、頻繁に洗濯したほうが良いでしょう。また、犬のベッドは皮脂汚れやよだれなどが付きやすく、ニオイの元になります。ペット用の消臭スプレーをこまめに噴霧し、月に1回は洗濯しましょう。犬が舐めたり噛んだりする可能性のある布製品を洗いたい場合、市販のペット用洗剤を使うと安心です。
おしっこが付いた場所はしっかりケアする
犬が粗相をしてしまったら、おしっこを拭き取ってペット用消臭スプレーをかけましょう。何度か繰り返して完全に拭き取ったら、仕上げに消臭スプレーを吹きかけておきます。
また、室内に設置している犬用トイレの周辺にニオイが残ってしまうことは珍しくありません。トイレシーツの範囲でおしっこをしていても、周辺に飛び散っていることがあります。トイレ周りの壁や床にもしっかりと消臭スプレーをかけ、拭き取り掃除をしましょう。
脱臭機や空気清浄機を導入し、ニオイ予防する
犬のニオイなどのペット臭は常に発生するものなので、気になるニオイが部屋に付着してしまう前に、脱臭機や空気清浄機で予防することもおすすめの方法です。高い脱臭効果※1が期待できる「次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ」なら、ニオイが染み込む前はもちろん、付着臭を脱臭することもできます。排泄時のニオイもすみやかに脱臭し、ニオイを抑えることが可能です。
また、「ジアイーノ」は静電HEPAフィルター※2を搭載しており、ほこりやチリ、抜け毛などをしっかりとキャッチします。汚れやニオイ物質をキャッチすることができるため、ペットとの暮らしをより快適にすることができます。
犬の臭い(ニオイ)対策をするなら空間除菌・脱臭にも力を入れましょう
犬のニオイの原因や対策のコツなどをご紹介しました。犬の体を清潔に保っていたとしても、たくさんの動物が集まる場所ではニオイが強くなってしまうことがあります。脱臭機で、空間そのもののニオイ対策を行うことがおすすめです。本体内部で次亜塩素酸水溶液を生成し、空気を除菌★・脱臭※1できる「ジアイーノ」なら、不快なニオイもすみやかに脱臭できます。導入に際して気になる点があれば、どうぞお気軽にお問い合わせください。
★ 浮遊菌の場合:約6畳(25m³)の密閉空間における、10分後の効果※3 付着菌の場合:約18畳(74m³)の試験空間における、45分後の効果※4 数値は実際の使用空間での試験結果ではありません
※1:「ジアイーノ」の脱臭効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、臭気によって異なります。
※2:JIS Z 8122:2000による規定 定格流量で粒径が0.3µmの粒子に対して99.97%以上の粒子捕集率をもち、かつ初期圧力損失が245Pa以下の性能をもつエアフィルタ
※3:【試験機関】一般財団法人 北里環境科学センター 【試験方法】約6畳(25m³)の密閉空間で、浮遊させた菌数の変化を測定 【除菌の方法】次亜塩素酸空間除菌脱臭機(F-JDU75)を風量「強」・チャージレベル「高」運転で実施 【対象】浮遊した菌 【試験結果】10分後に99%以上抑制(北生発 2021_1230 号)
※4:【試験機関】一般財団法人 北里環境科学センター 【試験方法】約18畳(74m³)の試験空間で、室内中央と室内奥に置いたシャーレに付着させた菌数の変化を測定 【除菌の方法】次亜塩素酸空間除菌脱臭機(F-JDU75)を風量「強」・チャージレベル「高」運転で実施 【対象】シャーレに付着した菌 【試験結果】45分後に99%以上抑制(北生発 2021_0370 号)