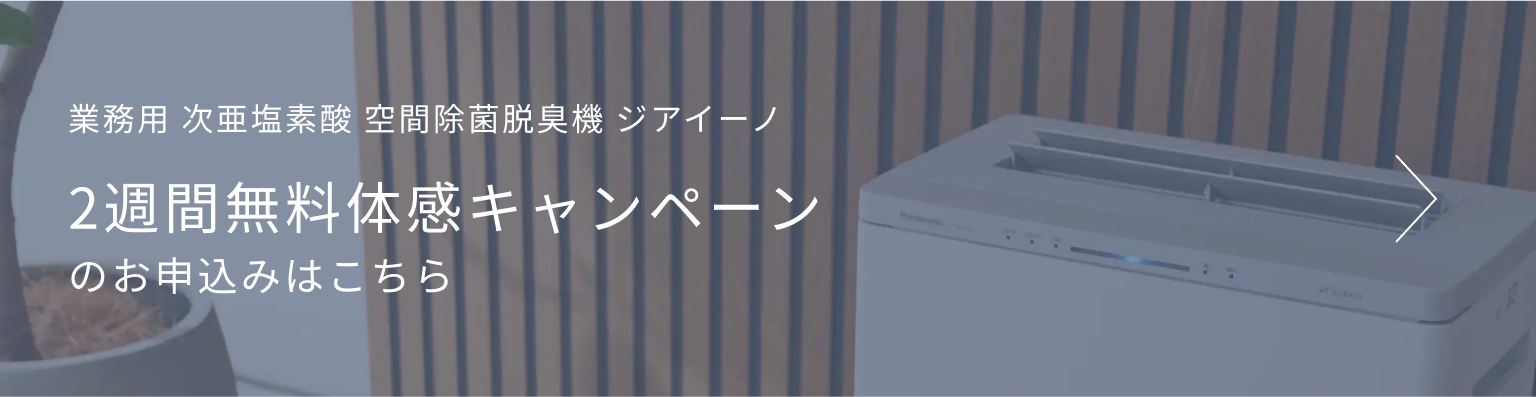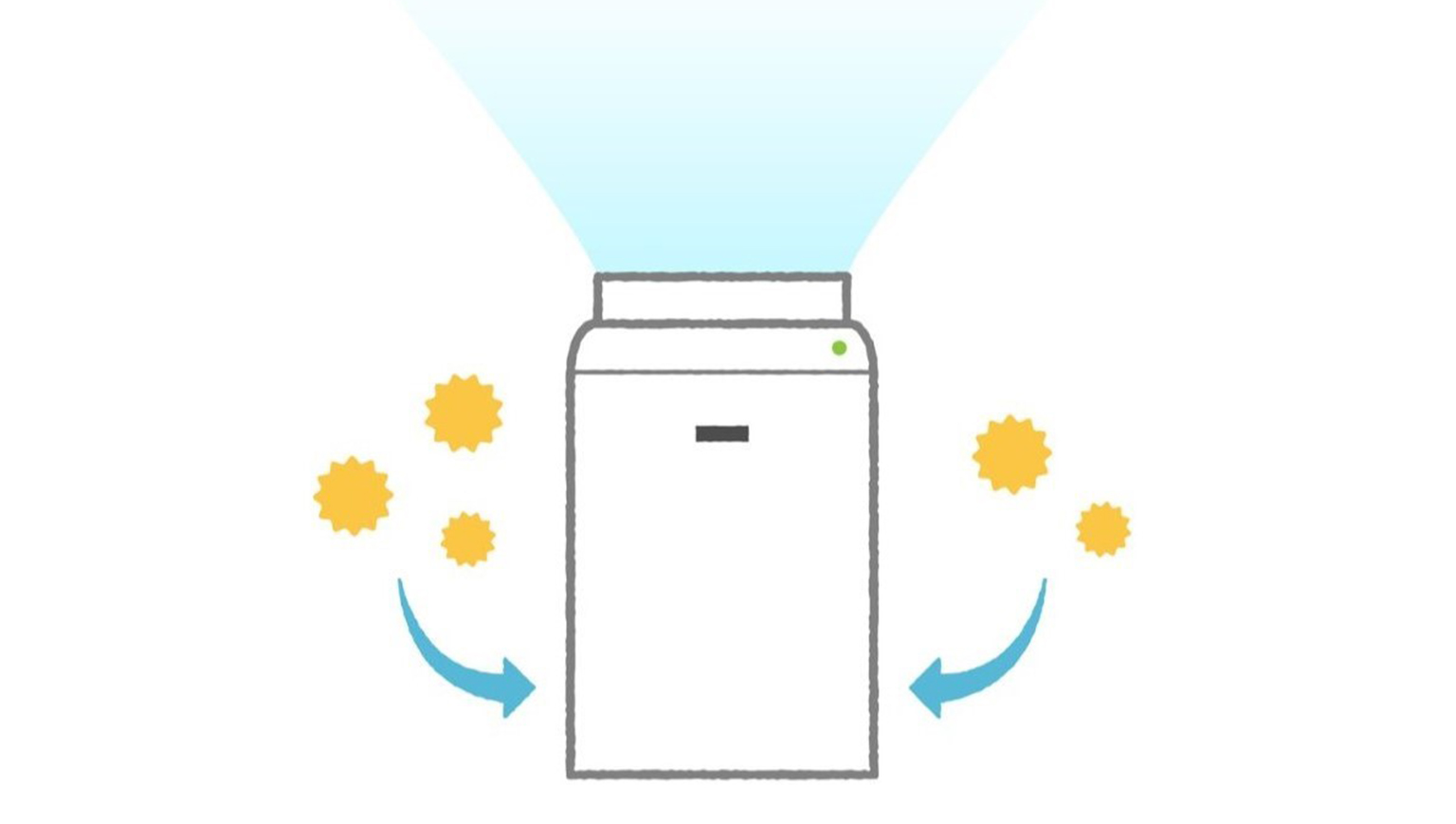猫の臭い(ニオイ)対策とは?主な原因やニオイを抑えるポイント

猫はもともと狩猟動物であることから、ほとんどニオイがないとされています。それは、狩りをする際、獲物に気付かれないように自分のニオイを抑えて待ち伏せする必要があるためです。それでは、なぜ猫のいる空間のニオイが気になってしまうのでしょうか。
この記事では、猫のニオイの主な原因や、ニオイ対策について解説します。猫と過ごす空間をより快適にするために、ぜひ参考にしてみてください。
目次
猫の臭い(ニオイ)の主な原因
初めに、猫のニオイの主な原因として考えられることをご紹介します。ニオイの悩みを解決するため、以下のポイントをチェックしてみましょう。
トイレのニオイ
猫のいる空間で気になるニオイは、主にトイレのニオイが原因だと考えられています。トイレの周辺や砂などが汚れていないでしょうか。猫は排泄後に砂をかける習性があるので、猫の足に汚れがついて、トイレ周りを汚してしまうことが少なくありません。また、きちんと掃除をしていたとしても、汚れた猫砂が十分に取り除けていないとニオイが残ってしまいます。
猫の身体から発生するニオイ
前述したように、猫のニオイの原因は主に尿や糞によるものです。基本的に猫は体臭が強くないとされていますが、身体からニオイが発せられる場合もあります。
例えば、猫も含めた動物の毛は、温まるとニオイが強くなる性質があります。よって、日光浴している猫から香ばしいニオイが発せられるときもあります。
また、鼻や肉球の汗によりポップコーンのようなニオイが生じることもあります。
ちなみに、猫の唾液は無臭で消臭効果があり、毛づくろいをすることで、猫は自らニオイを消していると言われています。ただし、病気やケガで毛づくろいができないと身体のニオイが気になってしまうことがあります。
これら以外にも、以下のように身体の特定の場所からニオイが発生しているケースもあります。
口のニオイ
猫の口臭は、口腔内のケア不足による口内炎や歯周病の可能性が高いとされます。口内炎の症状の例として、「口腔内に赤い腫れや出血が見られる」「ヨダレを垂らす」などが挙げられます。歯周病の症状として挙げられるのは、「歯石の付着」「歯茎の腫れ」「歯が抜ける」などです。また、口腔内の乾燥やキャットフードのニオイが口臭の原因となるケースも存在します。その他にも胃腸や腎臓の病気が原因で、口臭が発生するケースもあります。
おしりのニオイ
特に長毛種の猫は、肛門まわりの毛にうんちが付着しやすく、おしりのニオイの原因となることがあります。また、肛門腺液(=猫の肛門腺の分泌物)もおしりのニオイの原因として考えられるでしょう。体質や病気などで肛門腺液が分泌できずに溜まってしまうと、強烈な臭いを発することがあります。
おしっこのニオイ
猫のおしっこには、他の動物とは違う刺激臭があります。その理由は、腎臓から分泌される「コーキシン」というたんぱく質が、尿の中で「フェリニン」というアミノ酸を作り、空気に触れることで強いニオイを放つためです。フェリニンは去勢していないオスのおしっこに特に多く含まれています。
一方、おしっこからツンと鼻をつくようなアンモニア臭がする場合、細菌性膀胱炎などの病気が疑われます。日頃からおしっこに変化が現れていないか、しっかりとチェックしてあげましょう。いつもと違うニオイを感じた場合は、動物病院に相談することが大切です。
エサの食べ残しなどのニオイ
猫が食べ残したエサが腐敗して不快なニオイの原因となる場合があります。食べ終わった食器をそのまま放置していると、ニオイが部屋に拡散しやすくなります。
猫のいる空間の臭い(ニオイ)対策
猫のいる空間のニオイ対策として、日頃から取り組みたいことをご紹介します。猫がいる空間を掃除する際は、以下の対策方法を意識しましょう。
おしっこやうんちを放置しない
猫の排泄物を放置すると、部屋に悪臭が広がってしまいます。トイレの後はできるだけ早く片づけてあげましょう。もしもトイレ周りや壁が汚れてしまったら、消臭スプレーや抗菌タイプのウェットティッシュを使って掃除します。猫がトイレからはみ出して排泄してしまうなら、トイレ周りに消臭シートやペットシーツなどを敷き、こまめに取り替えましょう。
猫のトイレをきれいにする
猫のトイレは、1週間~1カ月に1回程度を目安に、やわらかいスポンジと中性洗剤を使って丸洗いすると良いでしょう。トイレを洗うタイミングで砂を丸ごと交換します。また、猫の足裏についた砂を落とすマットを使うと、砂がトイレ周りに飛び散りにくくなります。
食べ残しはすぐに片付ける
ニオイ対策のためにも、猫がエサを食べ残したらすぐに片づけることが重要です。また、使った食器はそのまま放置せず、しっかりと洗って乾かすようにします。普段から食べ残しが多い場合は、必要に応じて与えるエサの量の調節も検討すると良いでしょう。
換気をする
猫がいる空間の窓を締め切ったままにすると、猫のトイレのニオイなどが室内にこもりやすくなります。そのため、猫のトイレは窓がある風通しの良い部屋に置いて、定期的に換気するのがポイントです。特に夏場はニオイを強く感じやすいので、換気を欠かさないようにしましょう。
空間除菌脱臭機を使う
猫のいる空間のニオイ対策には、空間除菌脱臭機の使用がおすすめです。ペット臭のような常に発生し続けるニオイを脱臭し、猫と一緒に暮らす空間の空気を快適に保ちます。「次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ」は、気になるペット臭をしっかり脱臭※できるのが魅力です。猫のうんち・おしっこの強いニオイがお部屋に染みつく前に脱臭する効果が期待できます。また、すでにお部屋についてしまったニオイまで、気体状の次亜塩素酸で脱臭します。
猫の身体から発生する臭い(ニオイ)を軽減するポイント
基本的に猫は体臭が強くないとされていますが、先ほど述べたように、毛や口、おしりなど、猫の身体からニオイが発生することがあります。猫の身体のニオイを軽減するには、以下の点に注意しましょう。
定期的に猫のブラッシングをする
猫が適切にグルーミング(=毛づくろい)できないと身体のニオイにつながることがあります。グルーミングが苦手な猫や、高齢・病気などの理由でグルーミングができない猫には、猫用のブラシで定期的にブラッシングしてあげましょう。なお、「皮膚にブツブツがある」「猫が痒がっている」といったケースでは、肌の異常からニオイが発生している可能性があります。その際はブラッシングを避けて早めに動物病院で診てもらうようおすすめします。
猫の口腔ケアをする
猫の口腔ケアのために、定期的に猫用歯ブラシで歯磨きをしてあげましょう。また、デンタルケア効果のあるおやつやおもちゃを使うのも一つの手です。それでも口のニオイが気になるときは、動物病院で歯のトラブルや病気がないか診てもらうのが望ましいでしょう。
猫のおしりのケアをする
猫のおしりにうんちが付いていたら、濡らしたガーゼやペット用のシートで優しく拭いてあげてください。ただ、強く拭き過ぎたり、頻繁に拭いたりすると炎症を起こしてしまうおそれがあるため注意が必要です。長毛種の場合は、トリミングの際におしり周りの毛をカットしてもらうと、うんちが付きにくくなります。
猫のおしりの肛門腺絞りをする
肛門腺絞りとは、肛門腺液(=猫の肛門腺の分泌物)が溜まっているときに必要な処理です。肛門腺液は、うんちをするとき自然と排出されることが多いので、基本的に絞る必要はありません。ただ、猫がおしりを床にこすり付けたり、おしりを気にして舐めていたりしたら、肛門腺液が溜まっている可能性が考えられます。肛門腺絞りはコツがいるので、かかりつけの動物病院で対応してもらうと安心です。
必要な場合にはシャンプーを行う
猫は毛づくろいで、自らの身体を清潔に保つことができるため、基本的にシャンプーは必要ありません。
ただし、排泄物で身体が汚れてしまった場合や、高齢で毛づくろいができない場合など、自らの毛づくろいで清潔に保てないときはシャンプーをしてあげましょう。
猫の臭い(ニオイ)対策ではこまめなお掃除と適切なケアが大切!
ここまで、猫のニオイ対策について解説しました。一般的に、猫のいる空間のニオイが気になる場合、主にトイレのニオイが原因となるケースが多いといえます。猫のおしっこやうんちは速やかに片づけて、トイレをきれいに掃除してあげましょう。それでも猫がいる空間のニオイが気になる場合は、「次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ」がおすすめです。
「ジアイーノ」は一時的なニオイはもちろん、24時間発生するガンコなニオイにも効果を発揮※します。部屋に漂うペット臭にも対応可能です。「ジアイーノ」の脱臭力が気になる方は、ぜひお気軽にご相談ください。
※:「ジアイーノ」の脱臭効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、臭気によって異なります。