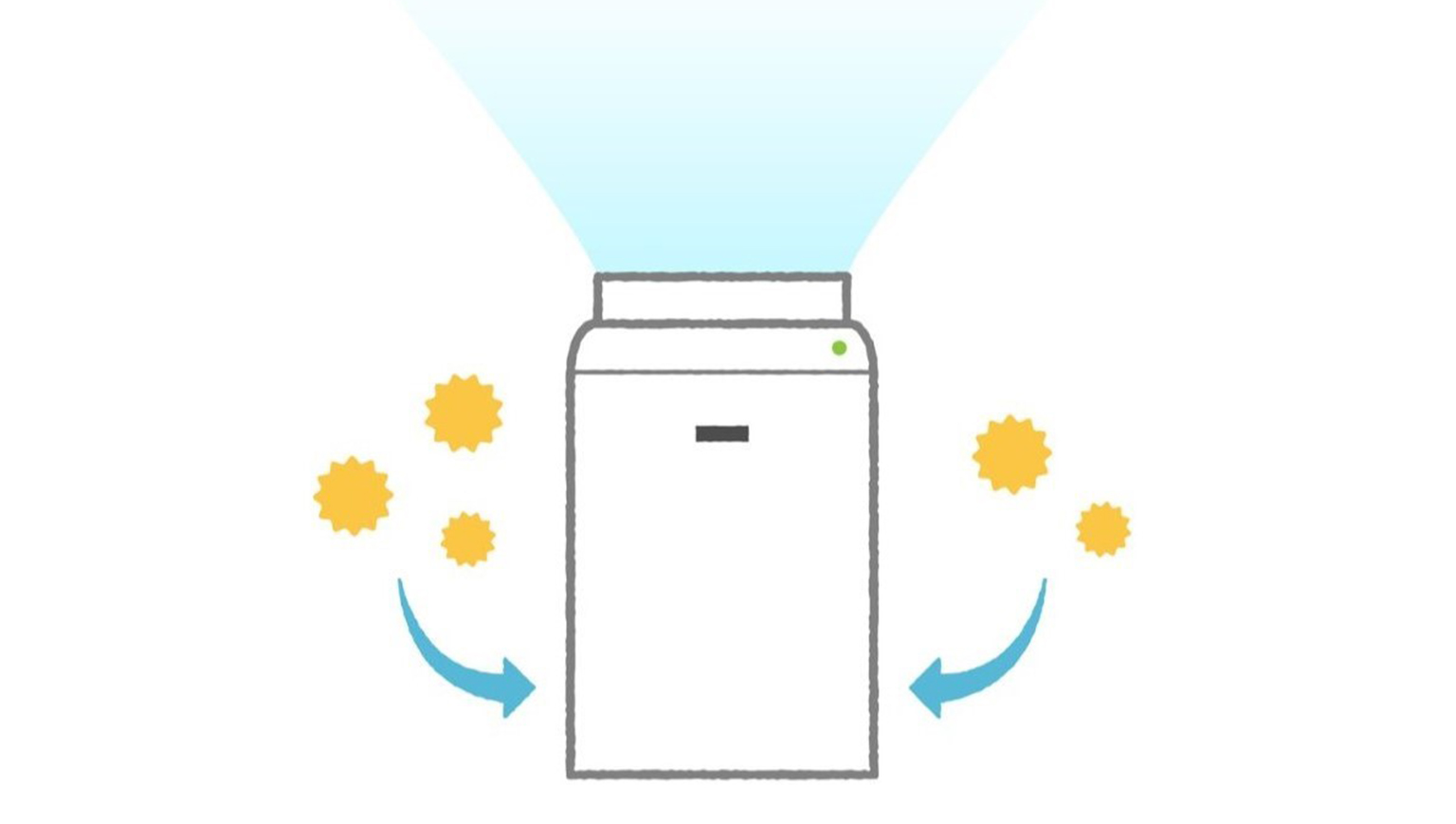老人ホームの掃除の仕方は?掃除する際のポイントと注意点

高齢者が利用する老人ホームの清潔さを保つことは、快適な暮らしの提供などの観点から、施設運営において重要な要素の一つです。とはいえ、着替えや食事、入浴の介助のほか、レクリエーションや介護記録の作成など、日々たくさんの業務に追われている職員の方にとっては、なるべく効率的に清潔な環境を維持することが求められます。そこで今回は、老人ホームで掃除が必要になる主要な場所ごとの掃除のポイントに加え、除菌・ニオイ対策についても解説します。
目次
老人ホームにおいて掃除が必要となる主な場所
老人ホームでの掃除は、基本的に毎日行う「日常清掃」と日常清掃では落としきれない汚れを除去する「定期清掃」、そして専門的な知識が求められる「特殊清掃」に分類できます。その中でも、職員の方が日々関わるのが日常清掃です。ここでは、日常清掃すべき場所ごとに、それぞれの掃除のポイントを解説します。
玄関・エレベーター・階段
玄関やエレベーター、廊下、階段は、利用者や職員だけでなく、利用者の家族や見学者など多くの方が行き交う場所です。
共用部の掃除が行き届いているかどうかで、施設の雰囲気や印象は大きく変わります。そのため、ゴミやホコリの除去、簡単な拭き掃除などは日常的に行いましょう。特に下駄箱などの汚れやすく、目立ちやすい箇所は重点的に掃除すべきです。また、不特定多数の人が触れる部分は除菌シートなどで拭き取ることも重要です。
食堂
老人ホームの食堂では、食後のテーブルや椅子の汚れはもちろん、床に落ちている食べカスなども掃除を行いましょう。床の食べこぼしを放置すると、汚れがこびりついて落としにくくなるだけでなく、車椅子などで踏まれてしまうと、汚れが広がってしまいます。そのため、なるべく早く掃除機やモップなどで取り除くことが重要です。
掃除スタッフを採用している老人ホームでも、とろみ食やきざみ食などが乾いてしまう前に、気付いたらすぐに拭き取ることが求められます。
居室
居室ではモップやダスターを使った床掃除のほか、ベッド回りの掃除、定期的なゴミの回収などを行います。個室は利用者の性格やその日の状態によって状況が異なるため、プライバシーや利用者の意思を尊重しながら整理整頓をして、清潔さを保てるよう心がけましょう。
トイレ・洗面台
トイレや洗面台は特に汚れが気になる場所であり、ニオイの原因となるリスクが高いため、見えない部分まで気を配って掃除する必要があります。特に利用者が直接触れるところは重点的に掃除しましょう。
浴室
浴室もトイレや洗面所と同じく、徹底した掃除が求められます。浴室の排水溝や床・壁・ドアのカビといった、汚れが溜まりやすい場所を中心に掃除をしてください。
老人ホームの掃除におけるポイント
老人ホームの掃除のポイントを5つ紹介します。
水回りは特に丁寧に掃除する
トイレ、浴室などの水回りは、汚れが目立ちやすく悪臭の原因にもなるため、特に丁寧に掃除しましょう。汚れたままにしていると、湿気の多い環境で繁殖しやすい細菌などの微生物やウイルスが繁殖してしまう恐れがあります。
例えば、トイレは便座の裏や便座同士の隙間、ウォシュレットのノズル部分などの汚れがたまりやすい箇所を普段からこまめに掃除しましょう。
また、浴槽のお湯の交換や、浴槽、床、壁の掃除も定期的に行いましょう。
空調などのフィルターの掃除も定期的に行う
老人ホームの施設内を快適な環境に保つためには、エアコンなどの空調システムの正常な稼働が不可欠です。エアコンのフィルターが汚れたままだと、空気の質が悪化して花粉・ダニ・カビなどの雑菌が室内に蔓延してしまいます。定期的にフィルターを取り外して掃除し、適切なタイミングで部品の交換をしましょう。
また、エアコン内部の汚れはフィルターを掃除・交換しても取り除けません。例えば、カバーの奥にはハウスダウトの元になるダニの死骸やフン、カビの胞子などが含まれたガンコなホコリが付着していることがあります。これらの汚れを除去するには、専門知識を持つ清掃業者によるクリーニングが必要です。
日常的な掃除・換気を徹底する
老人ホームの日常的な掃除は、施設内のチリ・ホコリを拭き取りによって除去することが重要です。掃除を徹底することで、利用者だけでなく訪問者からのイメージアップにもつながります。
また、人がよく触れる箇所は重点的にアルコール除菌スプレーなどで対策をしましょう。
さらに定期的な換気を行うことで、部屋にこもったし尿臭や加齢臭などへの対策にもなります。
高頻度接触表面と低頻度接触表面に分ける
老人ホームでは掃除すべき箇所が多いため、介護業務と並行しながらすべてを丁寧に掃除することは難しいでしょう。そのため、日常掃除すべき箇所を「高頻度接触表面」と「低頻度接触表面」に分類して、掃除の優先度を調整することをおすすめします。
よく触れられる「高頻度接触表面」のような箇所は必ず1日1回は掃除するほか、汚れを見つけたらすぐに掃除するなど、汚れのレベルに応じて掃除の回数を増やしましょう。一方、あまり人が直接触れない「低頻度接触表面箇所」については、高頻度接触表面よりも優先度が低いため、1日1回ではなく、適宜掃除を行うことで負担を軽減しつつ、清潔な環境を維持できるよう工夫しましょう。
用途に合った消毒液を選ぶ
雑巾やクロスに含ませる消毒液には様々な種類がありますが、基本的には病院で推奨されるレベルのものを選ぶのが望ましいです。各消毒液には、取扱方法や保管・廃棄方法、危険性などを記した「安全データシート(SDS)」が記載されています。SDSは日本ならびに海外でも表示が義務化されている仕組みであり、各現場に適した消毒液を選ぶ際の基準にするとよいでしょう。
具体的には、菌への対策として「低水準消毒薬」もしくは「消毒用エタノール」を用いることが一般的です。
出典:厚生労働省_職場のあんぜんサイト「安全衛生キーワード/SDS」
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo07_1.html
「次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ」で快適・清潔な環境をつくりましょう
老人ホームの掃除は、利用者やその家族が快適に過ごすための環境をつくる、重要な仕事の一つです。ただ、居室や食堂、廊下などの共用部のほか、トイレや浴室など、清潔に保たなければならない場所が多いうえ、介助や書類作成といった業務と並行して行っている現場も少なくないでしょう。
また、多くの人が共同生活する老人ホームにおいては、「空気」も清潔に保つ必要があります。空調のフィルター掃除はもちろん、こまめな換気を心がけることが重要です。
老人ホームの空気環境を清潔に保つのにおすすめなのが「次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ」です。「ジアイーノ」は、次亜塩素酸水溶液によって清潔除菌★・脱臭※3を行い、静電HEPAフィルター※4による集じん機能※5※6も搭載されています。
日常的な掃除に加えて行いたい除菌・集じん対策や、老人ホームのニオイに対する脱臭効果※3も期待できるので、施設の衛生管理でお悩みの方は、ぜひお問い合わせください。
★浮遊菌の場合:約6畳(25m³)の密閉空間における、10分後の効果※1 付着菌の場合:約18畳(74m³)の試験空間における、45分後の効果※2 数値は実際の使用空間での試験結果ではありません。
※1:【試験機関】一般財団法人 北里環境科学センター 【試験方法】約6畳(25m³)の密閉空間で、浮遊させた菌数の変化を測定 【除菌の方法】次亜塩素酸空間除菌脱臭機(F-JDU75)を風量「強」・チャージレベル「高」運転で実施 【対象】浮遊した菌 【試験結果】10分後に99%以上抑制(北生発 2021_1230 号)
※2:【試験機関】一般財団法人 北里環境科学センター 【試験方法】約18畳(74m³)の試験空間で、室内中央と室内奥に置いたシャーレに付着させた菌数の変化を測定 【除菌の方法】次亜塩素酸空間除菌脱臭機(F-JDU75)を風量「強」・チャージレベル「高」運転で実施 【対象】シャーレに付着した菌 【試験結果】45分後に99%以上抑制(北生発 2021_0370号)
※3:「ジアイーノ」の脱臭効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、臭気によって異なります。
※4: JIS Z 8122:2000による規定 定格流量で粒径が0.3µmの粒子に対して99.97%以上の粒子捕集率をもち、かつ初期圧力損失が245Pa以下の性能をもつエアフィルタ
※5:【試験機関】一般財団法人 北里環境科学センター 【試験方法】約6畳(25m³)の密閉空間で浮遊させた菌を、次亜塩素酸「あり」「なし」で次亜塩素酸 空間除菌脱臭機(F-JDU55)を運転し、HEPAフィルターに捕捉させた菌数の変化を比較 【対象】HEPAフィルターに捕捉した菌 【試験結果】60分後に99%以上抑制(北生発 2022_0185号)
※6:【試験機関】一般財団法人 北里環境科学センター 【試験方法】約6畳(25m³)の密閉空間で浮遊させたウイルスを、次亜塩素酸「あり」「なし」で次亜塩素酸 空間除菌脱臭機(F-JDU55)を運転し、HEPAフィルターに捕捉させたウイルス数の変化を比較 【対象】HEPAフィルターに捕捉したウイルス 【試験結果】30分後に99%以上抑制(北生発 2022_0186号)