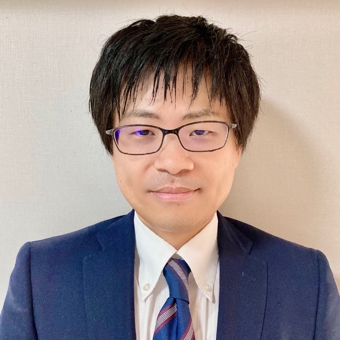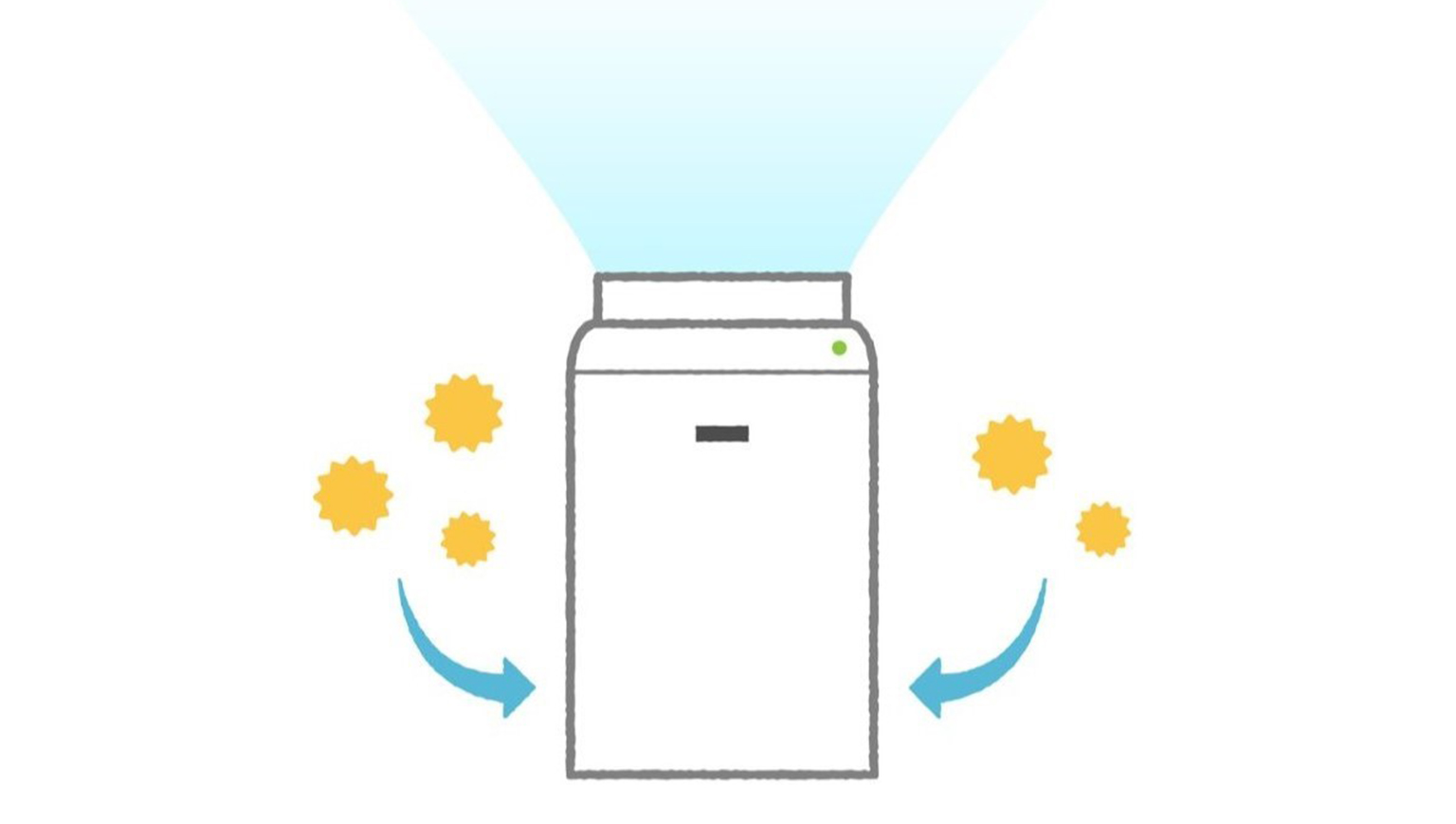空気清浄機の減価償却とは?一括償却や少額減価償却、仕訳の例

空気清浄機を生産性の向上などの目的で、オフィスや事務所などに設置する企業は少なくありません。事業目的で購入して使用する場合は経費処理の対象になりますが、空気清浄機の種類によって金額や必要な台数などは異なるため、事前にどのように処理するのか把握しておく必要があるでしょう。そこで今回は、空気清浄機の減価償却について解説します。
目次
空気清浄機の減価償却の概要
オフィスや介護施設、病院などで広く使用される空気清浄機は、法人や個人事業主が事業用に購入する場合、その購入代金を経費として処理できます。ただし、空気清浄機の経費処理については、一括で経費処理するケースと、減価償却という手続きを通じて経費処理するケースの2種類が存在します。ここではまず、空気清浄機の購入代金について減価償却を通じて経費処理する場合の、基本的な考え方を解説していきます。
空気清浄機の減価償却とは
法人や個人事業主が事業用に購入した空気清浄機は、その取得価額や耐用年数によって、一括で経費計上できる場合と、減価償却を行う必要がある場合に分かれます。
ここでの減価償却とは、取得した資産の価値を耐用年数にわたって分割し会計年度ごとに費用として計上する会計処理のことを指します。例えば、空気清浄機を購入し、その取得価額が一定額を超える場合、購入した年度に全額を経費として計上することはできません。そのため、財務省の定める耐用年数に基づいて減価償却を行う必要があります。減価償却の手続きによって、1年間で全額経費処理するのではなく、複数年にわたって経費の計上を行っていきます。
そもそも、事業や業務で使用される建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両などの資産は、通常、時間の経過とともに価値が減少していく資産です。このような資産は「減価償却資産」と呼ばれ、減価償却の対象となります。
減価償却資産は、時間の経過とともに価値が減少していくため、減価償却を通じてその価値を適正に把握します。そのため、減価償却資産を取得する際にかかった費用は、購入時に全額を経費として計上するのではなく、その資産が使用できる期間にわたって分割して経費処理する必要があります。例えば、100万円の減価償却資産を購入し、これを5年間使用する場合、100万円を使用可能期間(5年)で均等に割るため、1年間で20万円を減価償却費として計上します。
減価償却資産の耐用年数は、経営者や個人事業主が自由に決めることはできません。もし、自由に決められると、1年間の減価償却額を恣意的に決定できてしまうためです。そこで、財務省令の別表において使用可能期間が定められています。使用可能期間は厳密には「法定耐用年数」と呼ばれ、取得した減価償却資産は、法定耐用年数に従って減価償却し、経費として計上します。
原則として、耐用年数が1年未満又は取得価額10万円未満のものは減価償却資産(固定資産)として計上せず、購入時に一括して経費計上します。空気清浄機についても、この原則的な取扱いに準じて会計処理しなければなりません。
参考:国税庁「No.2100 減価償却のあらまし」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm
参考:e-Gov「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」
https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000040015/
空気清浄機の法定耐用年数
それでは、空気清浄機の法定耐用年数は、何年と定められているのでしょうか。上記の財務省令の別表には、さまざまな減価償却資産の法定耐用年数が示されているものの、具体的な機器の法定耐用年数は明示されていません。そこで、空気清浄機については、「電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器」に該当すると解釈して、6年間が法定耐用年数となります。
出典:国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/pdf/2100_01.pdf
空気清浄機の減価償却の仕訳例
空気清浄機を事業用に購入した際、その購入金額によって、減価償却の対象となるかどうかが決まります。具体的には、取得価額が10万円未満の場合は購入時に全額を経費計上できる一方で、10万円以上の場合は固定資産として計上し、耐用年数にわたって減価償却を行う必要があります。
また、消費税の処理方法によっても、減価償却の対象となるかどうかが異なります。税込経理方式では税込価格で判定し、税抜経理方式では税抜価格で判定するため、注意が必要です。例えば税抜経理だと95,000円で「全額経費」であり、税込経理方式だと104,500円となり「固定資産計上」になり、同じ価格の空気清浄機を購入したとしても処理の仕方が変わってしまうのです。ここでは、それぞれのケースに応じた具体的な仕訳例を解説していきます。
購入金額が10万円未満の場合の仕訳例
取得価額が10万円未満の空気清浄機は、固定資産として計上する必要がなく、購入時に一括で経費として処理することが可能です。これは、少額資産として扱われるため、減価償却を行わず、消耗品費や器具備品費として全額をその年の経費にできるためです。税抜経理方式で95,000円となるケースの仕訳例を以下で確認してみましょう。
仕訳例1(税抜経理方式で95,000円の空気清浄機を購入する場合
・税抜経理方式(消費税抜きで判断する場合)
消耗品費(または器具備品費) 95,000円 / 現金(または預金) 95,000円
仮払消費税等 9,500円 / 現金(または預金) 9,500円
なお、税抜経理方式では、仕訳時に「仮払消費税等」を別途計上する点に注意が必要です。
購入金額が10万円以上の場合の仕訳例
購入時(固定資産計上)
空気清浄機の取得価額が10万円以上の場合は、固定資産(器具備品)として計上し、耐用年数6年にわたって減価償却を行います。税込経理方式で104,500円となるケースの仕訳例を以下で確認してみましょう。
・税込経理方式(消費税込みで104,500円の場合)
器具備品 104,500円 / 現金(または預金) 104,500円
※税込104,500円のため、減価償却資産として計上。
減価償却費の計上(耐用年数6年・定額法)
取得価額104,500円(税込)を6年の耐用年数で定額法によって償却する場合、 毎年の減価償却費は以下のように計上します。
減価償却費 17,416円 / 減価償却累計額 17,416円
※10,500円÷ 6年=17,416円(1円未満切り捨て)
したがって、10万円以上の空気清浄機は購入時に固定資産として計上し、毎年減価償却を行う必要があります。上記のように購入時の消費税の処理方法によっても判定が異なるため、税込経理方式・税抜経理方式の違いを理解しておくことが重要です。
一括償却資産と中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例とは
通常、10万円以上の空気清浄機は耐用年数(6年)にわたって減価償却を行いますが、一定の条件を満たせば、特例を利用してより短期間で経費計上することができます。特例には以下の2つの方法があります。
1. 一括償却資産(10万円以上20万円未満)→3年間で均等償却
2. 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(30万円未満)→購入年度に全額経費計上(※中小企業者などのみ)
中小企業者等に関しては、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(以下、少額減価償却資産)を適用すると取得年度の法人税や所得税の負担を大きく減らすことができるので、設備投資を行ったことで資金繰りが厳しくなっている場合には有利な選択となります。
一方で、償却資産税においては、少額減価償却資産を適用した場合には課税対象となるのに対して、一括償却資産として処理した場合には課税対象とならないため、一括償却資産として処理した方が有利な選択となります。
このため、自社の置かれた状況を踏まえてどちらを選択すべきか検討することが重要です。
一括償却資産とは
取得価額が10万円以上20万円未満の空気清浄機は、「一括償却資産」として処理できます。一括償却資産とは、耐用年数に関係なく3年間で均等償却できる資産のことです。通常、空気清浄機は法定耐用年数である6年で減価償却しますが、一括償却資産として処理すれば、3年間で償却できるため、より早期に経費計上が可能です。
「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」とは
取得価額が30万円未満の空気清浄機は、「中小企業者等の少額減価償却資産の特例」を利用すれば、購入年度に全額を経費として計上できます。この特例は、一定の中小企業や個人事業主が利用可能であり、次の条件を満たす必要があります。
●中小企業者等(青色申告の法人・個人事業主)
●従業員数500人以下
●資本金1億円未満の法人
●取得価額30万円未満の資産
●年間合計300万円までの購入額が対象(超過分は適用不可)
なお、中小企業者等の少額減価償却資産の特例を適用するには、資産を事業で使用した事業年度内に、その取得価額を損金として計上するとともに、確定申告の際に法人の場合は「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表16(7))」を添付し、個人事業主の場合は「減価償却費の計算」に「措法28の2」と記載して申告する必要があります。
一括償却資産(10万円以上20万円未満)と、少額減価償却資産(30万円未満)の両方に該当する場合、どちらの方法で会計処理をするかは、企業の財務状況や節税対策の観点から判断することが重要です。
少額減価償却資産の特例を利用して、「次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ」の導入検討も。
少額減価償却資産を活用すれば、30万円未満の設備を購入した際に、取得年度に全額を経費計上できるため、即時に節税効果を得ることができます。特例を利用することで、「次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ」を導入する際の負担も軽減できます。
「ジアイーノ」は、本体内部で次亜塩素酸水溶液を生成し、空気中の菌を除菌★し、不快なニオイを脱臭※3する機能を備えています。さらに集じん機能も搭載されており、さまざまな汚れや花粉などを効果的にキャッチ※4※5。事業場の清潔な空気環境を保つためのパートナーとなってくれるでしょう。
例えば、以下のような施設で活用されています。
●病院・クリニック(院内の空気環境改善)
●介護施設(入居者の生活空間の快適化)
●オフィス・会議室(清潔な職場環境の維持)
●飲食店・ホテル(衛生対策と快適な空間づくり) など
少額減価償却資産の特例を活用すれば、30万円未満の機種であれば購入年度に全額を経費計上でき、導入のハードルが下がります。事業所や施設の空気環境を改善したい方は、ぜひこの特例を活用しながら、「ジアイーノ」の導入をご検討ください。
★浮遊菌の場合:約6畳(25m³)の密閉空間における、10分後の効果※1付着菌の場合:約18畳(74m³)の試験空間における、45分後の効果※2数値は実際の使用空間での試験結果ではありません
※1:【試験機関】一般財団法人 北里環境科学センター【試験方法】約6畳(25m³)の密閉空間で、浮遊させた菌数の変化を測定 【除菌の方法】次亜塩素酸空間除菌脱臭機(F-JDU75)を風量「強」・チャージレベル「高」運転で実施【対象】浮遊した菌【試験結果】10分後に99%以上抑制(北生発 2021_1230号)
※2:【試験機関】一般財団法人 北里環境科学センター【試験方法】約18畳(74m³)の試験空間で、室内中央と室内奥に置いたシャーレに付着させた菌数の変化を測定【除菌の方法】次亜塩素酸空間除菌脱臭機(F-JDU75)を風量「強」・チャージレベル「高」運転で実施【対象】シャーレに付着した菌【試験結果】45分後に99%以上抑制(北生発 2021_0370号)
※3:「ジアイーノ」の脱臭効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、臭気によって異なります。
※4:【試験機関】一般財団法人 北里環境科学センター 【試験方法】約6畳(25m³)の密閉空間で浮遊させた菌を、次亜塩素酸「あり」「なし」で次亜塩素酸 空間除菌脱臭機(F-JDU55)を運転し、HEPAフィルターに捕捉させた菌数の変化を比較 【対象】HEPAフィルターに捕捉した菌 【試験結果】60分後に99%以上抑制(北生発 2022_0185号)
※5:【試験機関】一般財団法人 北里環境科学センター【試験方法】約6畳(25m³)の密閉空間で浮遊させたウイルスを、次亜塩素酸「あり」「なし」で次亜塩素酸 空間除菌脱臭機(F-JDU55)を運転し、HEPAフィルターに捕捉させたウイルス数の変化を比較 【対象】HEPAフィルターに捕捉したウイルス 【試験結果】30分後に99%以上抑制(北生発 2022_0186号)