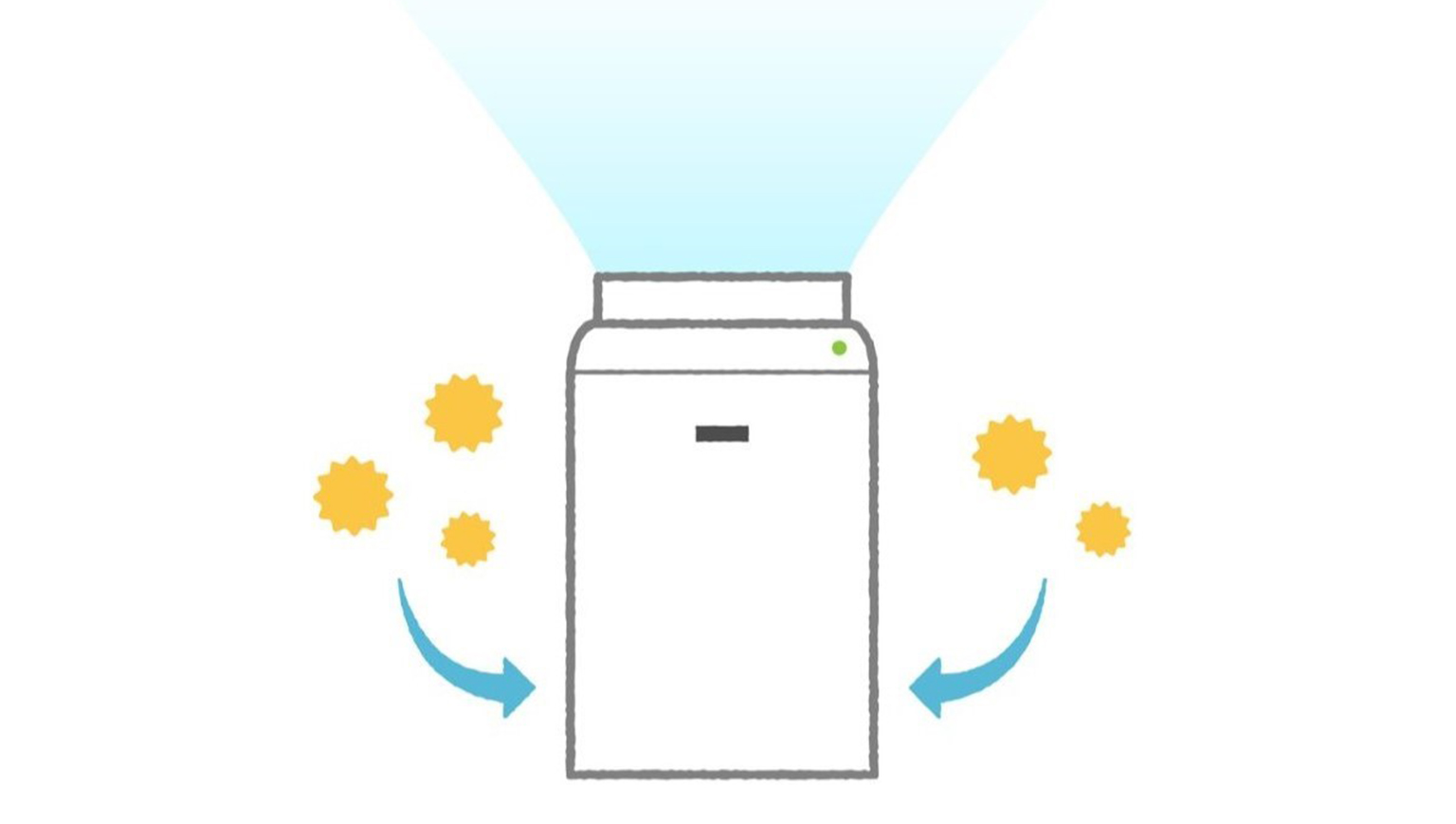職場の衛生管理はどのようにすれば良い?方法や職場巡視の流れ

職場やオフィスは従業員が長時間を過ごす場所であるため、職場環境を清潔に保つ必要があります。衛生管理が行き届いていない作業環境では、従業員の疲労やストレスが蓄積しやすく、集中力や作業効率にも悪影響を与えかねません。
本記事では、職場での衛生管理について解説し、快適な職場環境を作るための職場巡視の具体的な手順を紹介します。ぜひ最後までご覧ください。
目次
職場における衛生管理とは?
職場における衛生管理は、単に清潔な環境を提供するだけでなく、法律に基づいた適切な管理が求められます。
本章では、職場で求められる衛生管理について解説します。
職場の衛生管理とは
職場の衛生管理とは、従業員が快適に働ける職場環境を作ることを指します。職場では多くの従業員が一緒に仕事をするため、さまざまな配慮が必要です。従業員が快適に働ける環境を整えることが、事業者にとっての重要な責任となります。
職場環境が適切に管理されると、従業員にとって快適な労働環境が整います。例えば、定期的な換気や清掃、適切な温度・湿度コントロールは生産性の向上にもつながります。衛生管理を適切に維持するためには、法律や規則に基づいて取り組む体制が重要です。
●職場の衛生管理の必要性
衛生管理については労働安全衛生法で定められています。例えば、事業主は従業員の数に応じて、事業場専属の衛生管理者を選任する義務があり、違反した場合には罰金といった罰則が科される場合もあるのです。
なお、衛生管理者に選任される人物は誰でも良いわけではなく、選任には業種に応じた適切な資格や免許が必要です。例えば、「第一種衛生管理者」や「第二種衛生管理者」といった資格があります。
衛生管理者は、以下の業務を行います。
・健康被害の防止・ストレスチェック
・安全・衛生についての教育
・健康診断の実施
・労働災害の調査と再発防止
・衛生日誌の記載など
衛生管理者は最低でも週に1回職場を巡視し、衛生状態に問題があれば、迅速な対応が求められます。
参考:厚生労働省 「衛生管理者について教えて下さい。」
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/5.html
出典:厚生労働省_職場のあんぜんサイト「衛生管理者」
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo33_1.html
職場の衛生管理のポイント
職場で衛生管理を行うにあたり、重要なポイントは以下の2点です。
・換気
・清掃
本章では上記について詳しく解説します。
換気の実施
人が多く集まる職場では、換気が重要です。
厚生労働省は窓を開けて部屋の空気を入れ替える際は「30分に一回以上、数分間程度、窓を全開する」といった換気方法を推奨しています。
出典:厚生労働省「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000618969.pdf
また、冬季のオフィス環境の基準では、職場内の「室温が17℃以上28℃以下、職場内の相対湿度が40%以上70%以下」であることが求められます。
出典:独立行政法人 労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所「冬季のオフィス環境における低湿度の実態と対策について」
https://www.jniosh.johas.go.jp/publication/mail_mag/2014/75-column-2.html
エアコン使用時は、冬は乾燥、夏は冷えすぎといった問題が発生しやすいため、窓やドアを開けて行う定期的な換気により、温度・湿度の適切な管理にもつながります。従業員に対して適切な環境管理の重要性を周知すると効果的です。
さらに、定期的な換気に加えて、空気清浄機の使用も検討しましょう。脱臭効果のあるタイプの空気清浄機を使用すると、職場のニオイ対策にも効果的です。
清掃の徹底
清掃の行き届いていない職場は、従業員のモチベーションや作業効率を低下させる可能性があります。そのため、定期的な清掃の実施や、ごみの分別は、従業員が快適に働ける職場環境を作るために不可欠です。
さらに、従業員への衛生教育・安全教育を実施し意識を高めるのも効果的です。例えば、会議室の使用後は使った椅子や机を除菌シートで拭くといった具体的な対策を実施するとよいでしょう。
また、多くの人が行き来する事業所内では、チリやホコリが舞いやすくなります。定期的な清掃は、職場における集じん対策にも効果的です。
職場の衛生管理に求められる「職場巡視」とは?
職場巡視は、衛生管理者が職場内を定期的に点検し、衛生状態や安全性を確認する重要な活動です。職場巡視はただ実施するだけではなく、PDCAサイクルの一環として改善までつなげる必要があります。
本章では、職場巡視の流れについて3つのステップに分けて具体的に解説します。
Step1.職場巡視の計画
まず、職場巡視を定期的に行うための年間計画を、作業環境や業務内容に合わせて作成します。
効率的に巡視が行えるよう職場内のマップを活用するなどして、巡視のタイミングやエリアの情報などを追記していきましょう。
事前に巡視対象となる項目をチェックリストとして整理しておくと、漏れなく確認でき、巡視がスムーズに進みます。
Step2.職場巡視の実施
では実際に、職場環境を巡視していきましょう。
チェック項目はさまざまですが、例えば以下の事項に注意し巡視を行い記録します。
・コード類や設備は整理整頓されているか
・休憩室やトイレなどの施設は清潔か
・保護具は適切に着用しているか
・騒音・防音対策はされているか
従業員が快適に働ける環境になるよう厳しく巡視し、事故の原因となり得る点は逃さずチェックしましょう。
Step3.報告書の作成
巡視の結果から改善が必要であったポイントは、リスク評価などを行ったうえで、チェックリストの結果とあわせて関係各所への報告・相談を行います。
報告書は、適切に職場巡視を行った証明にもなるため、一定期間適切な方法で保存しましょう。
報告書提出後は必要に応じ、以下の対応を行います。
・職場環境の改善
・安全衛生委員会への報告・審議
・残存リスクへの対応計画
定期的な巡視を通じて、危険の予知や改善策の実行を推進しましょう。
「次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ」で職場の衛生管理を効率的に!
従業員が快適に働くためには、職場での衛生管理が欠かせません。衛生管理の基本は、定期的な換気や清掃です。
職場の衛生管理をより効果的・効率的に行うなら、企業への納入事例も多い「次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ」がおすすめです。
「ジアイーノ」は、次亜塩素酸水溶液のチカラで清潔除菌★・脱臭※3。加齢臭などの発生し続けるニオイにも高い脱臭効果※3を発揮します。またチリ・ホコリなどの集じん機能も搭載※4※5されているため、多くの人が集まる職場での衛生管理に適しているといえるでしょう。
★浮遊菌の場合:約6畳(25立方メートル)の密閉空間における、10分後の効果※1 付着菌の場合:約18畳(74立方メートル)の試験空間における、45分後の効果※2 数値は実際の使用空間での試験結果ではありません。
※1:【試験機関】一般財団法人 北里環境科学センター【試験方法】約6畳(25m³)の密閉空間で、浮遊させた菌数の変化を測定 【除菌の方法】次亜塩素酸空間除菌脱臭機(F-JDU75)を風量「強」・チャージレベル「高」運転で実施【対象】浮遊した菌【試験結果】10分後に99%以上抑制(北生発 2021_1230号)
※2:【試験機関】一般財団法人 北里環境科学センター【試験方法】約18畳(74m³)の試験空間で、室内中央と室内奥に置いたシャーレに付着させた菌数の変化を測定【除菌の方法】次亜塩素酸空間除菌脱臭機(F-JDU75)を風量「強」・チャージレベル「高」運転で実施【対象】シャーレに付着した菌【試験結果】45分後に99%以上抑制(北生発 2021_0370号)
※3:「ジアイーノ」の脱臭効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、臭気によって異なります。
※4:【試験機関】一般財団法人 北里環境科学センター 【試験方法】約6畳(25m³)の密閉空間で浮遊させた菌を、次亜塩素酸「あり」「なし」で次亜塩素酸 空間除菌脱臭機(F-JDU55)を運転し、HEPAフィルターに捕捉させた菌数 の変化を比較 【対象】HEPAフィルターに捕捉した菌 【試験結果】60分後に99%以上抑制(北生発 2022_0185 号)
※5:【試験機関】一般財団法人 北里環境科学センター 【試験方法】約6畳(25m³)の密閉空間で浮遊させたウイルスを、次亜塩素酸「あり」「なし」で次亜塩素酸 空間除菌脱臭機(F-JDU55)を運転し、HEPAフィルターに捕捉させた ウイルス数の変化を比較 【対象】HEPAフィルターに捕捉したウイルス 【試験結果】30分後に99%以上抑制(北生発 2022_0186 号)